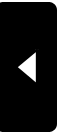鬼蜘蛛の網の片隅から › 教育
2012年11月13日
内藤朝雄著「いじめ加害者を厳罰にせよ」の主張と問題(3)
学級制度の廃止について
さて、内藤氏はいじめの解決のためには「学級制度の廃止」と「学校への法の導入(法に基づいた加害者の処罰)」を提唱する。前者はコミュニケーション操作系(シカトする、悪口を言う、嘲笑する等)のいじめに効果を発揮すると主張する。学級を廃止して、たとえば大学のように授業ごとに教室を移動して席を特定せず、食事も好きな相手と好きなところで食べ、班活動なども強制しないようにすることでいじめは効力を大幅に失うという。
このような発想自体は納得できるものだ。しかし、地方の過疎地などではそもそも学級が一つしかない小学校や中学校、高校が珍しくない。それどころか複式学級で一クラスが数人とか、全校生徒でも数人あるいは十数人などといった小学校すらある。給食も全校生徒が同じ教室で食べ、学年の枠すらすでにない。このような小規模校では、全校生徒での「仲良し」を強制される。力をもった高学年の子どもが下級生をいじめる状況になれば、被害者は逃げ場がない。「学級制度の廃止」は、小規模校に適用できる方法ではない。また、小学校では学級を廃止するのは現実的ではないだろう。
学級制度の廃止だけでは不十分である以上、「学校に行きたくない子どもが学校へ行かなくても学習を続けられる環境を整える」ことも必要ではないか。通信教育とか、家庭教師による学習とか、フリースクールの充実である。現在でも通信制や単位制の高校があるが、過疎地ではそれらの利用もままならない。今よりもっと手軽に、誰もが学校以外での学習を保証する制度が必要だと思う。
賛同できない加害者への刑事罰
内藤氏は、市民社会で暴力が目撃されれば警察に通報するのが当たり前だから、それと同じように学校での暴力を警察に通報すべきだという。学校は無法地帯であるうえ市民社会の常識が通用しない「学校モード」に支配されている。しかも学校には教育ムラがあり教師はいじめを隠蔽するので学校内部では解決ができない。だから一般社会のルールを持ち込むのがベストだという。
暴力系のいじめはすぐに止めさせるべきだという主張はもっともだが、その解決策として刑事罰をいきなり持ち出すのは賛同できない。刑事罰にはたしかに暴力行為をすぐに止めさせる効力はあるだろう。しかし同時にさまざまなデメリットやリスクを伴う。
まず報復ともいえる刑事罰でいじめの本質的問題が解決されるのかということ。もう一つは子どもの間の紛争の解決を警察という治外法権の国家権力に頼るべきことなのかという問題。警察では裏金が作られ警察官の違法行為も後を絶たないが、内部の犯罪には極めて甘い。捜査では相変わらず自白強要などの違法行為が絶えない。しかもこの国は厳罰化に向かっている。そういうところに解決を委ねるべきなのか。
私は過去に個人で2回警察に告発・告訴をしている。ひとつは悪質商法を行っている文芸社の詐欺疑惑の刑事告発。もう一つは私の個人情報を不正取得した行政書士への告訴。両方とも証拠資料等を添えて警察に告発状・告訴状を提出したが、警察は受け取ろうとすらしなかった。警察に被害届を出しても、明瞭な証拠がなければ警察はなかなか捜査に乗り出さない。しかし被害者自身がいじめられている証拠まで押さえるのは容易なことではない。被害届を出しても警察が速やかに動かなければ、加害者がさらに被害者を追い詰めることすらあり得るのではなかろうか。女性がストーカー行為で警察に被害を訴えたのに放置され、殺されてしまった事件も複数ある。
被害届や告訴に警察がきちんと対応し加害者を処罰したとしても被害者は刑事裁判に関われないし、被害への補償もなされない。また、加害者のいじめ行為の根底にストレスが関係しているのなら、動機や背景こそ解明されなければならないだろう。そうした解明がないまま刑罰を与えて、心からの反省や謝罪につながるだろうか。加害者に必要なのは刑罰より精神の安定化であり、カウンセラーや臨床心理士だ。刑事裁判を全否定するつもりはないが、個人間での争いの解決を刑事罰だけに期待するのはいろいろな意味で賛成できない。
かといって、監視社会にしてしまうのも恐ろしい。少し前の北海道新聞によると、近年は探偵事務所などに依頼していじめの調査をしてもらう親が増えているという。いじめの現場を動画などで撮影して学校に証拠として突き付けることで学校もいじめを否定できなくなるのだ。学校がいじめの隠蔽をする以上、いじめ現場の隠し撮りは確かに有効な方法だろう。しかし、これはどう考えても異常な事態だ。しかも、こうした方法は金銭的に余裕のある親しかできない。
刑事罰に異議を唱えれば、「それならどうやって被害者を救うのか?」という声が聞こえてきそうだ。次回は刑事罰以外の方法について書いてみたい。
内藤朝雄著「いじめ加害者を厳罰にせよ」の主張と問題(1)
内藤朝雄著「いじめ加害者を厳罰にせよ」の主張と問題(2)
内藤朝雄著「いじめ加害者を厳罰にせよ」の主張と問題(4)
内藤朝雄著「いじめ加害者を厳罰にせよ」の主張と問題(5)
さて、内藤氏はいじめの解決のためには「学級制度の廃止」と「学校への法の導入(法に基づいた加害者の処罰)」を提唱する。前者はコミュニケーション操作系(シカトする、悪口を言う、嘲笑する等)のいじめに効果を発揮すると主張する。学級を廃止して、たとえば大学のように授業ごとに教室を移動して席を特定せず、食事も好きな相手と好きなところで食べ、班活動なども強制しないようにすることでいじめは効力を大幅に失うという。
このような発想自体は納得できるものだ。しかし、地方の過疎地などではそもそも学級が一つしかない小学校や中学校、高校が珍しくない。それどころか複式学級で一クラスが数人とか、全校生徒でも数人あるいは十数人などといった小学校すらある。給食も全校生徒が同じ教室で食べ、学年の枠すらすでにない。このような小規模校では、全校生徒での「仲良し」を強制される。力をもった高学年の子どもが下級生をいじめる状況になれば、被害者は逃げ場がない。「学級制度の廃止」は、小規模校に適用できる方法ではない。また、小学校では学級を廃止するのは現実的ではないだろう。
学級制度の廃止だけでは不十分である以上、「学校に行きたくない子どもが学校へ行かなくても学習を続けられる環境を整える」ことも必要ではないか。通信教育とか、家庭教師による学習とか、フリースクールの充実である。現在でも通信制や単位制の高校があるが、過疎地ではそれらの利用もままならない。今よりもっと手軽に、誰もが学校以外での学習を保証する制度が必要だと思う。
賛同できない加害者への刑事罰
内藤氏は、市民社会で暴力が目撃されれば警察に通報するのが当たり前だから、それと同じように学校での暴力を警察に通報すべきだという。学校は無法地帯であるうえ市民社会の常識が通用しない「学校モード」に支配されている。しかも学校には教育ムラがあり教師はいじめを隠蔽するので学校内部では解決ができない。だから一般社会のルールを持ち込むのがベストだという。
暴力系のいじめはすぐに止めさせるべきだという主張はもっともだが、その解決策として刑事罰をいきなり持ち出すのは賛同できない。刑事罰にはたしかに暴力行為をすぐに止めさせる効力はあるだろう。しかし同時にさまざまなデメリットやリスクを伴う。
まず報復ともいえる刑事罰でいじめの本質的問題が解決されるのかということ。もう一つは子どもの間の紛争の解決を警察という治外法権の国家権力に頼るべきことなのかという問題。警察では裏金が作られ警察官の違法行為も後を絶たないが、内部の犯罪には極めて甘い。捜査では相変わらず自白強要などの違法行為が絶えない。しかもこの国は厳罰化に向かっている。そういうところに解決を委ねるべきなのか。
私は過去に個人で2回警察に告発・告訴をしている。ひとつは悪質商法を行っている文芸社の詐欺疑惑の刑事告発。もう一つは私の個人情報を不正取得した行政書士への告訴。両方とも証拠資料等を添えて警察に告発状・告訴状を提出したが、警察は受け取ろうとすらしなかった。警察に被害届を出しても、明瞭な証拠がなければ警察はなかなか捜査に乗り出さない。しかし被害者自身がいじめられている証拠まで押さえるのは容易なことではない。被害届を出しても警察が速やかに動かなければ、加害者がさらに被害者を追い詰めることすらあり得るのではなかろうか。女性がストーカー行為で警察に被害を訴えたのに放置され、殺されてしまった事件も複数ある。
被害届や告訴に警察がきちんと対応し加害者を処罰したとしても被害者は刑事裁判に関われないし、被害への補償もなされない。また、加害者のいじめ行為の根底にストレスが関係しているのなら、動機や背景こそ解明されなければならないだろう。そうした解明がないまま刑罰を与えて、心からの反省や謝罪につながるだろうか。加害者に必要なのは刑罰より精神の安定化であり、カウンセラーや臨床心理士だ。刑事裁判を全否定するつもりはないが、個人間での争いの解決を刑事罰だけに期待するのはいろいろな意味で賛成できない。
かといって、監視社会にしてしまうのも恐ろしい。少し前の北海道新聞によると、近年は探偵事務所などに依頼していじめの調査をしてもらう親が増えているという。いじめの現場を動画などで撮影して学校に証拠として突き付けることで学校もいじめを否定できなくなるのだ。学校がいじめの隠蔽をする以上、いじめ現場の隠し撮りは確かに有効な方法だろう。しかし、これはどう考えても異常な事態だ。しかも、こうした方法は金銭的に余裕のある親しかできない。
刑事罰に異議を唱えれば、「それならどうやって被害者を救うのか?」という声が聞こえてきそうだ。次回は刑事罰以外の方法について書いてみたい。
内藤朝雄著「いじめ加害者を厳罰にせよ」の主張と問題(1)
内藤朝雄著「いじめ加害者を厳罰にせよ」の主張と問題(2)
内藤朝雄著「いじめ加害者を厳罰にせよ」の主張と問題(4)
内藤朝雄著「いじめ加害者を厳罰にせよ」の主張と問題(5)
2012年11月12日
内藤朝雄著「いじめ加害者を厳罰にせよ」の主張と問題(2)
学校モードはいつから生じたのか
内藤氏自身がかつていじめ被害者であっただけに、いじめを生み蔓延させるメカニズムは真を突いている。
まず、内藤氏は学校という場を以下のように表現している。
こうやって並べてみるなら、学校は「強制」のかたまりだ。私は、学校という「強制収容所」でベタベタした集団生活を強要されることがいじめの温床となるという内藤氏の主張はもっともだと思う。
また内藤氏は、子どもたちは学校で集団生活を送ることで「学校モード」と呼ぶべき特殊な心理状態になり、市民社会では「悪いこと」されるいじめが、学校モードでは「良いこと」となってしまうという。このために残酷ないじめに加担する「怪物」になるという。子どもたちに「学校モード」が存在するということも事実だろう。
ところで内藤氏は、長期にわたっていじめが増加しているデータはなく、いじめが残酷化してきているとは言えないとしている。本当にそうだろうか?
学校での様々な強制は今にはじまったものではない。私が学校に通っていた1960年代初めから1970年代も同じだ。しかし、その頃と今では明らかに子どもたちの感覚に違いが生じている。
何が違うのか・・・。私の経験から考えるなら、私が小学生の頃は「学校モード」は内藤氏が指摘するほど明確に確立されてはいなかったといえる。たしかに学校では嫌がらせ、悪口、無視、暴力などのいじめはあったが、子どもたちは学校でも「いじめ」が悪いことであると認識しており、いじめをする子においそれと同調はしなかった。だから、いじめられる子が孤立しているというより、いじめる子が非難されるという状況があった。学校はたしかに強制が多く窮屈な場ではあったが、市民社会での常識もそれなりに存在していた。
いわゆる反抗期に当たる中学時代も、少数だが先生に反抗的な態度をとる生徒がいた。しかし、多くの生徒はそうした生徒に安易に同調したりはせず、むしろ醒めた目で見ていた気がする。中学・高校時代にも、皆に同調しないマイペース型、あるいはガリ勉タイプの生徒は必ずクラスに一人や二人はいた。そういう生徒は概して友だちがいないか少ないのだが、それでも陰湿ないじめにまで発展しないのが普通だった。そのような生徒にとって学校が苦痛ではあっても自殺するほどの苦痛の場にはなっていなかったように思う。
生徒の多くは気の合う者同士で付き合い、お互いに干渉することはあまりなかったように思う。もちろん悪口、陰口の類はあったが、集団での「シカト」「無視」にまで発展することは少なかった。もちろん、私の知らないところで陰湿ないじめもあったのだろうが、それは一般的ではなかったと思う。
「皆に同調する」ということに関して、内藤氏は「ノリ」という表現を使っている。つまり、その場の「ノリ」に神経を尖らせ、皆に合わせていることが学校モードでは要求されるというのだ。そしてみんなの「ノリ」に従わずに「浮いて」いることは「悪い」ことで、「浮いて」いるにも関わらず、自信を持って生きているのは「とても悪い」ことになり、身分的に下の者が人並みの自損感情を持つことは「すごく悪い」という。
ならば、私などは学校に通っていた頃から今に至るまで「すごく悪い」の典型だ。多くの女子グループが話題にしている異性やタレントの話しなど興味がなかったし、趣味も読んでいた本も周りの生徒とはかなり異なっていた。高校時代に陰口を言われていたことも知っている。それでも陰湿ないじめに遭うことはなかった。たぶん私のようなタイプは、今の学校ではまっさきにいじめのターゲットになっているのだろう。つまり、かつてはたとえ「浮いて」いて「わが道を行く」タイプであっても、それはそれで許容されていたのである。
しかし、今はあきらかに違う。「みんなに同調しない者は悪である」という「学校モード」がどこの学校にも明瞭に存在し、子どもたちは否応なしに自分が「浮かない」ように緊張を強いられている。
このように、一般社会の常識が通じない強固な「学校モード」が昔からずっとあったとは思えないのである。明瞭な「学校モード」がいつ頃から確立されてきたのかはわからないが、1980年代のはじめ頃ではなかろうか。私と同年代で今年の3月に亡くなった渡辺容子さんはかつて学童保育の指導員をしていたのだが、子どもたちと接している中で、彼女も同じ変化をはっきりと感じ取っていたという。
子どもたちは明らかにかつてより「皆と同じにしなければならない」という強迫観念に強く捉われるようになってきている。私にはその変化とともに、いじめが頻発化、残酷化していると思えてならない。ならば、いじめの蔓延の原因は「強制収容所」だけにあるのではなく、もっと複合的なものと言えないだろうか。
「皆と同じが良くて、異質なものはダメ」という考えは、なにも学校に通う子どもたちに限った感覚ではない。実は、親自身がそうした感覚を以前よりより強く持つようになっているのではないかと思えてならない。
私が住んでいる北海道の地方の町でもそういう傾向は強い。たとえばある親がスキー学習のために子どもにメーカー品のスキー用具やウェアを一式買いそろえると、他の親も次々と真似をして同じような物を買い与える。マウンテンバイクが流行れば、わが子が仲間外れになってはいけないとばかりに買い与える。そんな光景が日常的に見られた。
親が「自分の子どもが流行りに乗り遅れたらいじめられる」と、先取りしてしまう。また、親自身が保護者集団の中で特定の親のいじめをすることもあった。その理由は「皆と違う」である。つまり、社会全体に「皆と同じにしていることがいい」「異質なものは叩き排除する」という内藤氏の言うところの「全体主義」がはびこってきている。かつての「村八分」である。これでは、子どもたちの間に「皆と違っていてもいい」という感覚が生まれるはずもない。もちろん親がこのような意識になっているのも社会的背景があるはずだ。
子どもたちが親から「皆と違っていたらいけない」と刷り込まれれば、「皆と違う子はいじめていい」という意識ももちかねない。学校という強制収容所と「皆と同じが良くて、違うことは悪い」という価値観、全体主義が結びつくことで、いじめすら「良いこと」とされる強固な「学校モード」が確立されていったのではなかろうか。
学校では「学校モード」という特殊な心理状態になるという内藤氏の論理は理解できる。しかし、子どもたちだって日々のニュースによって、人を傷つけたり暴力をふるうことが犯罪であり悪いことであるくらい十分理解しているはずだ。いじめをストレス発散の場として楽しむ加害者グループも、そんなことは分かり切っている。
善悪の判断ができる子どもが、「学校モード」になると陰湿ないじめすら悪いと思わないという感覚に陥ってしまうのは、学校という場が治外法権の強制収容所ということだけでは説明がつかない。かつては学校にもそれなりに存在していた社会常識、倫理といったものがなぜ消えてしまったのか・・・。
本書にはこうした指摘が見当たらない。どのようにして異常な「学校モード」が確立されたのかの考察なしに強制システムだけを問題視する単純さが私には疑問だ。
内藤朝雄著「いじめ加害者を厳罰にせよ」の主張と問題(1)
内藤朝雄著「いじめ加害者を厳罰にせよ」の主張と問題(3)
内藤朝雄著「いじめ加害者を厳罰にせよ」の主張と問題(4)
内藤朝雄著「いじめ加害者を厳罰にせよ」の主張と問題(5)
内藤氏自身がかつていじめ被害者であっただけに、いじめを生み蔓延させるメカニズムは真を突いている。
まず、内藤氏は学校という場を以下のように表現している。
役人が便宜上引いた学区というエリアの中にある学校に、それまでほとんど縁がなかった子どもたちが義務教育(小中学校の場合)の名の下に「強制出頭」させられ、「同年齢だから」という理由だけでひとまとめにされる(学年制度)。さらに、それを30~40人に分けられ、朝から夕方まで窮屈な部屋に「軟禁」される(学級制度)。クラスでは一人一人の能力を無視した「集団学習」が行われ、刑務所や軍隊のような「集団摂食」を強要される。グループを組まされて反活動に「動員」されたり、掃除などの「不払い労働」に従事させられる―。(34ページ)
こうやって並べてみるなら、学校は「強制」のかたまりだ。私は、学校という「強制収容所」でベタベタした集団生活を強要されることがいじめの温床となるという内藤氏の主張はもっともだと思う。
また内藤氏は、子どもたちは学校で集団生活を送ることで「学校モード」と呼ぶべき特殊な心理状態になり、市民社会では「悪いこと」されるいじめが、学校モードでは「良いこと」となってしまうという。このために残酷ないじめに加担する「怪物」になるという。子どもたちに「学校モード」が存在するということも事実だろう。
ところで内藤氏は、長期にわたっていじめが増加しているデータはなく、いじめが残酷化してきているとは言えないとしている。本当にそうだろうか?
学校での様々な強制は今にはじまったものではない。私が学校に通っていた1960年代初めから1970年代も同じだ。しかし、その頃と今では明らかに子どもたちの感覚に違いが生じている。
何が違うのか・・・。私の経験から考えるなら、私が小学生の頃は「学校モード」は内藤氏が指摘するほど明確に確立されてはいなかったといえる。たしかに学校では嫌がらせ、悪口、無視、暴力などのいじめはあったが、子どもたちは学校でも「いじめ」が悪いことであると認識しており、いじめをする子においそれと同調はしなかった。だから、いじめられる子が孤立しているというより、いじめる子が非難されるという状況があった。学校はたしかに強制が多く窮屈な場ではあったが、市民社会での常識もそれなりに存在していた。
いわゆる反抗期に当たる中学時代も、少数だが先生に反抗的な態度をとる生徒がいた。しかし、多くの生徒はそうした生徒に安易に同調したりはせず、むしろ醒めた目で見ていた気がする。中学・高校時代にも、皆に同調しないマイペース型、あるいはガリ勉タイプの生徒は必ずクラスに一人や二人はいた。そういう生徒は概して友だちがいないか少ないのだが、それでも陰湿ないじめにまで発展しないのが普通だった。そのような生徒にとって学校が苦痛ではあっても自殺するほどの苦痛の場にはなっていなかったように思う。
生徒の多くは気の合う者同士で付き合い、お互いに干渉することはあまりなかったように思う。もちろん悪口、陰口の類はあったが、集団での「シカト」「無視」にまで発展することは少なかった。もちろん、私の知らないところで陰湿ないじめもあったのだろうが、それは一般的ではなかったと思う。
「皆に同調する」ということに関して、内藤氏は「ノリ」という表現を使っている。つまり、その場の「ノリ」に神経を尖らせ、皆に合わせていることが学校モードでは要求されるというのだ。そしてみんなの「ノリ」に従わずに「浮いて」いることは「悪い」ことで、「浮いて」いるにも関わらず、自信を持って生きているのは「とても悪い」ことになり、身分的に下の者が人並みの自損感情を持つことは「すごく悪い」という。
ならば、私などは学校に通っていた頃から今に至るまで「すごく悪い」の典型だ。多くの女子グループが話題にしている異性やタレントの話しなど興味がなかったし、趣味も読んでいた本も周りの生徒とはかなり異なっていた。高校時代に陰口を言われていたことも知っている。それでも陰湿ないじめに遭うことはなかった。たぶん私のようなタイプは、今の学校ではまっさきにいじめのターゲットになっているのだろう。つまり、かつてはたとえ「浮いて」いて「わが道を行く」タイプであっても、それはそれで許容されていたのである。
しかし、今はあきらかに違う。「みんなに同調しない者は悪である」という「学校モード」がどこの学校にも明瞭に存在し、子どもたちは否応なしに自分が「浮かない」ように緊張を強いられている。
このように、一般社会の常識が通じない強固な「学校モード」が昔からずっとあったとは思えないのである。明瞭な「学校モード」がいつ頃から確立されてきたのかはわからないが、1980年代のはじめ頃ではなかろうか。私と同年代で今年の3月に亡くなった渡辺容子さんはかつて学童保育の指導員をしていたのだが、子どもたちと接している中で、彼女も同じ変化をはっきりと感じ取っていたという。
子どもたちは明らかにかつてより「皆と同じにしなければならない」という強迫観念に強く捉われるようになってきている。私にはその変化とともに、いじめが頻発化、残酷化していると思えてならない。ならば、いじめの蔓延の原因は「強制収容所」だけにあるのではなく、もっと複合的なものと言えないだろうか。
「皆と同じが良くて、異質なものはダメ」という考えは、なにも学校に通う子どもたちに限った感覚ではない。実は、親自身がそうした感覚を以前よりより強く持つようになっているのではないかと思えてならない。
私が住んでいる北海道の地方の町でもそういう傾向は強い。たとえばある親がスキー学習のために子どもにメーカー品のスキー用具やウェアを一式買いそろえると、他の親も次々と真似をして同じような物を買い与える。マウンテンバイクが流行れば、わが子が仲間外れになってはいけないとばかりに買い与える。そんな光景が日常的に見られた。
親が「自分の子どもが流行りに乗り遅れたらいじめられる」と、先取りしてしまう。また、親自身が保護者集団の中で特定の親のいじめをすることもあった。その理由は「皆と違う」である。つまり、社会全体に「皆と同じにしていることがいい」「異質なものは叩き排除する」という内藤氏の言うところの「全体主義」がはびこってきている。かつての「村八分」である。これでは、子どもたちの間に「皆と違っていてもいい」という感覚が生まれるはずもない。もちろん親がこのような意識になっているのも社会的背景があるはずだ。
子どもたちが親から「皆と違っていたらいけない」と刷り込まれれば、「皆と違う子はいじめていい」という意識ももちかねない。学校という強制収容所と「皆と同じが良くて、違うことは悪い」という価値観、全体主義が結びつくことで、いじめすら「良いこと」とされる強固な「学校モード」が確立されていったのではなかろうか。
学校では「学校モード」という特殊な心理状態になるという内藤氏の論理は理解できる。しかし、子どもたちだって日々のニュースによって、人を傷つけたり暴力をふるうことが犯罪であり悪いことであるくらい十分理解しているはずだ。いじめをストレス発散の場として楽しむ加害者グループも、そんなことは分かり切っている。
善悪の判断ができる子どもが、「学校モード」になると陰湿ないじめすら悪いと思わないという感覚に陥ってしまうのは、学校という場が治外法権の強制収容所ということだけでは説明がつかない。かつては学校にもそれなりに存在していた社会常識、倫理といったものがなぜ消えてしまったのか・・・。
本書にはこうした指摘が見当たらない。どのようにして異常な「学校モード」が確立されたのかの考察なしに強制システムだけを問題視する単純さが私には疑問だ。
内藤朝雄著「いじめ加害者を厳罰にせよ」の主張と問題(1)
内藤朝雄著「いじめ加害者を厳罰にせよ」の主張と問題(3)
内藤朝雄著「いじめ加害者を厳罰にせよ」の主張と問題(4)
内藤朝雄著「いじめ加害者を厳罰にせよ」の主張と問題(5)
2012年11月09日
内藤朝雄著「いじめ加害者を厳罰にせよ」の主張と問題(1)
内藤氏の主張
内藤朝雄氏の「いじめ加害者を厳罰にせよ」(ベスト新書)が10月に発行された。本書は、大津市の中学生のいじめ自殺事件がマスコミで大きく取り上げたことをきっかけに、いじめ問題の第一人者ともいえる内藤氏が、いじめのメカニズムとその解決策を訴えたものだ。私自身は「いじめ加害者を厳罰にせよ」というタイトルに驚きを禁じ得ないが、このタイトルには一刻も早くいじめ被害者をなくしたいという内藤氏の思いが込められているのだろう。
内容的には、内藤氏がこれまで主張してきたことを誰にでも分かるように解説した本といえる。しかし、内藤氏の主張を知らなかった人にとっては、「目からうろこ」といえるような主張かもしれない。なぜなら、内藤氏の主張はマスコミに登場する教育評論家や著名人などの持論とはかなりかけ離れたものであり、日本社会に浸透しているとは思えないからだ。それどころか、内藤氏はマスコミでばら撒かれる些末ないじめ対策はむしろ有害であると批判しているのである。
私は内藤氏の論じるいじめのメカニズムは評価するのだが、刑事罰導入による解決策は賛同できないし、不十分あるいは不適切だと思う部分もある。そこで、この本を読んで気づいた感じたことについて、何回かに分けて書いてみたいと思う。
内藤氏の主張について考えるために、まず本書での彼の主張の要旨を以下にまとめてみた。
【いじめに関する誤解】
・長期にわたっていじめの件数が増えていることを示す信頼できる統計はない。
・1979年、1986年にも残酷で陰湿ないじめ事件が報道されており、近年になって残酷化したとは言えない。
・いじめは子どもたちだけの問題ではなく、あらゆるところに存在する。
・イギリスやノルウェーでも残忍ないじめ事例がある。
・教育評論家や著名人などによる「いじめ論」は矛盾だらけである。
【いじめのメカニズム】
・市民社会では悪とされるいじめが、学校では「当たり前」「良いこと」になってしまう。これは「市民社会モード」と「学校モード」の違いからくる。
・学校という「強制収容所」でベタベタした集団生活を強要されることがいじめの温床となる。
・生徒の選択肢は、①仲良くしたくないクラスメイトやグループと友だちになることを拒否し、孤独で過ごす。②自分の自然な重いや感情は諦め、自分をいじめる加害者も含めがクラスメイトやグループと友だちになる。という二者択一しかない。
・「学校モード」では、みんなに同調せず「浮いている」(「ノリ」に従わない)者、いじめの「チクリ」をする者がもっとも嫌われいじめの対象とされる。
・いじめ加害者は「損か得か」という利害で行動する。
・いじめには暴力系のいじめ(殴る、蹴る、衣服を脱がせる等)、とコミュニケーション操作系のいじめ(シカトする、悪口を言う、嘲笑する等)がある。
・長くつづくタイプのいじめは、加害者グループが被害者を囲い込み、表面上は友だちを装いながら家畜を飼育するかのように躾け玩具にする「友だち家畜」と言うべき「飼育タイプ」が主流である。
【いじめの隠蔽構造】
・学校や教育委員会がいじめを隠蔽するのは、利害関係でつながる「教育ムラ」のため。ムラの安泰のために隠蔽が行われる。
・保護者や地元民が被害者の親に嫌がらせをすることで教育ムラの隠蔽に加担することもある。
・有名人等の「心の問題」にフォーカスさせるコメントをマスコミが報じることが、状況を悪化させる。
【いじめ解決策】
・長中期的な教育制度の抜本的改革は短期間では実現できないので、まずは短期的な解決策を実施することが重要。
・短期的解決策は「学級制度の廃止」と「学校への法の導入(法に基づいた加害者の処罰)」である。
・「学校制度の廃止」は「コミュニケーション操作系」のいじめに効果を発揮する。
・「暴力系のいじめ」に対しては、市民社会の法を学校内の暴力に持ち込み加害者を処罰することが有効である。
これ以外に、少年法や厳罰に反対するいわゆる「人権派」に関しての意見、個人でのいじめへの対処法などにも触れられている。これについては後で言及したいが、ここでは割愛する。
おそらく内藤氏の主張は、いじめの被害者にとって、非常にすんなりと受け入れられるものだろう。被害者は、加害者がなんら制裁を受けずに大きな顔をしてのさばり、被害者ばかりが苦しみに耐える状態に置かれていることに大きな矛盾や怒りを感じているからだ。
内藤朝雄著「いじめ加害者を厳罰にせよ」の主張と問題(2)
内藤朝雄著「いじめ加害者を厳罰にせよ」の主張と問題(3)
内藤朝雄著「いじめ加害者を厳罰にせよ」の主張と問題(4)
内藤朝雄著「いじめ加害者を厳罰にせよ」の主張と問題(5)
内藤朝雄氏の「いじめ加害者を厳罰にせよ」(ベスト新書)が10月に発行された。本書は、大津市の中学生のいじめ自殺事件がマスコミで大きく取り上げたことをきっかけに、いじめ問題の第一人者ともいえる内藤氏が、いじめのメカニズムとその解決策を訴えたものだ。私自身は「いじめ加害者を厳罰にせよ」というタイトルに驚きを禁じ得ないが、このタイトルには一刻も早くいじめ被害者をなくしたいという内藤氏の思いが込められているのだろう。
内容的には、内藤氏がこれまで主張してきたことを誰にでも分かるように解説した本といえる。しかし、内藤氏の主張を知らなかった人にとっては、「目からうろこ」といえるような主張かもしれない。なぜなら、内藤氏の主張はマスコミに登場する教育評論家や著名人などの持論とはかなりかけ離れたものであり、日本社会に浸透しているとは思えないからだ。それどころか、内藤氏はマスコミでばら撒かれる些末ないじめ対策はむしろ有害であると批判しているのである。
私は内藤氏の論じるいじめのメカニズムは評価するのだが、刑事罰導入による解決策は賛同できないし、不十分あるいは不適切だと思う部分もある。そこで、この本を読んで気づいた感じたことについて、何回かに分けて書いてみたいと思う。
内藤氏の主張について考えるために、まず本書での彼の主張の要旨を以下にまとめてみた。
【いじめに関する誤解】
・長期にわたっていじめの件数が増えていることを示す信頼できる統計はない。
・1979年、1986年にも残酷で陰湿ないじめ事件が報道されており、近年になって残酷化したとは言えない。
・いじめは子どもたちだけの問題ではなく、あらゆるところに存在する。
・イギリスやノルウェーでも残忍ないじめ事例がある。
・教育評論家や著名人などによる「いじめ論」は矛盾だらけである。
【いじめのメカニズム】
・市民社会では悪とされるいじめが、学校では「当たり前」「良いこと」になってしまう。これは「市民社会モード」と「学校モード」の違いからくる。
・学校という「強制収容所」でベタベタした集団生活を強要されることがいじめの温床となる。
・生徒の選択肢は、①仲良くしたくないクラスメイトやグループと友だちになることを拒否し、孤独で過ごす。②自分の自然な重いや感情は諦め、自分をいじめる加害者も含めがクラスメイトやグループと友だちになる。という二者択一しかない。
・「学校モード」では、みんなに同調せず「浮いている」(「ノリ」に従わない)者、いじめの「チクリ」をする者がもっとも嫌われいじめの対象とされる。
・いじめ加害者は「損か得か」という利害で行動する。
・いじめには暴力系のいじめ(殴る、蹴る、衣服を脱がせる等)、とコミュニケーション操作系のいじめ(シカトする、悪口を言う、嘲笑する等)がある。
・長くつづくタイプのいじめは、加害者グループが被害者を囲い込み、表面上は友だちを装いながら家畜を飼育するかのように躾け玩具にする「友だち家畜」と言うべき「飼育タイプ」が主流である。
【いじめの隠蔽構造】
・学校や教育委員会がいじめを隠蔽するのは、利害関係でつながる「教育ムラ」のため。ムラの安泰のために隠蔽が行われる。
・保護者や地元民が被害者の親に嫌がらせをすることで教育ムラの隠蔽に加担することもある。
・有名人等の「心の問題」にフォーカスさせるコメントをマスコミが報じることが、状況を悪化させる。
【いじめ解決策】
・長中期的な教育制度の抜本的改革は短期間では実現できないので、まずは短期的な解決策を実施することが重要。
・短期的解決策は「学級制度の廃止」と「学校への法の導入(法に基づいた加害者の処罰)」である。
・「学校制度の廃止」は「コミュニケーション操作系」のいじめに効果を発揮する。
・「暴力系のいじめ」に対しては、市民社会の法を学校内の暴力に持ち込み加害者を処罰することが有効である。
これ以外に、少年法や厳罰に反対するいわゆる「人権派」に関しての意見、個人でのいじめへの対処法などにも触れられている。これについては後で言及したいが、ここでは割愛する。
おそらく内藤氏の主張は、いじめの被害者にとって、非常にすんなりと受け入れられるものだろう。被害者は、加害者がなんら制裁を受けずに大きな顔をしてのさばり、被害者ばかりが苦しみに耐える状態に置かれていることに大きな矛盾や怒りを感じているからだ。
内藤朝雄著「いじめ加害者を厳罰にせよ」の主張と問題(2)
内藤朝雄著「いじめ加害者を厳罰にせよ」の主張と問題(3)
内藤朝雄著「いじめ加害者を厳罰にせよ」の主張と問題(4)
内藤朝雄著「いじめ加害者を厳罰にせよ」の主張と問題(5)
2012年07月16日
内藤朝雄氏の指摘するいじめの論理と解決への提言
大津市の中学校のいじめ事件のことについて、マスコミが毎日のように報道している。焦点となっているのは学校や教育委員会の真相隠し。そして、このようないじめ事件に対し決まり文句のように「原因の究明」「再発の防止」「命を大切にする教育」という言葉が繰り返される。
学校での凄惨ないじめは今にはじまったことではない。いじめが社会問題として深刻化するようになってからいったい何年が経ったのだろう。事件が明るみになる度に「原因の究明」「再発の防止」が叫ばれているが、一向に改善の兆しは見られない。言葉ばかりが空回りしているようで虚しい。悲惨な事件が報道されるたびに、多くの人が加害者や教育関係者に怒りをあらわにしているのだが、そこにも解決の糸口を見つけることはできない。
いじめのメカニズムを解き明かし、いじめ解決への提言を行っているのが社会学者の内藤朝雄氏だ。内藤氏は「いじめの社会理論」(柏書房)という本のまえがきで以下のように述べている。
内藤氏は本書でいじめが生じる仕組みを非常に明確に解き明かしている。いじめがおきる原因は、加害者や被害者、教育関係者といった個々の人たちの問題ではない。集団の心理に起因するのであり、学校だけではなくどこでも起こりうるという指摘は非常に納得のいくものだ。学校や社会で強いられる「なかよしごっこ」、「屈従関係」が人々の自由と人格権を奪っているというのは、まさにその通りだろう。
内藤氏は、学校という共同体では以下のような状況が生じるという。
これらのことはどこの集団にも存在しており誰もが経験しているだろう。こうした共同体による強制がいじめを生むのである。内藤氏は、いじめのない社会の構築のために、一人ひとりがそれぞれにとっての望ましい生のスタイルときずなを生きることができる「自由な社会」を提言する。このような社会では「なじめない者の存在を許す我慢(寛容)」が要求されるものの、「なかよしごっこ」をしない権利が保障されるのだ。
ただし、このような社会は放っておけばできるというものではない。社会的な基盤が必要だ。こうした社会の実現のために以下の要件をあげている。
そして、現行の強制的に集団生活を課す義務教育を廃止し、あらたな学習体系による教育制度を提言する。いじめ大国、自殺大国になってしまった日本において、熟考されるべき提言だろう。
思い返せば、私も学校は大嫌いだった。学校には主流派による無言の強制があり、そこから外れてしまえば非難の視線があった。でも私はたいてい主流派の中にはいなかった。だから本当の気持ちを心の奥底にしまい、いつも不満を抱えていた。自分を殺して協調性を重んじるなんてまっぴらだったし、人の顔色ばかりうかがっている人が嘘っぽく見えた。何よりも集団に拘束されず自由な自分でいられる休日が楽しみで、解放感にひたれる夏休みを待ち焦がれていた。
内藤さんの本を読むと、学校が大嫌いだった理由がストンと胸に落ちるのだ。私が学校に通っていた頃は今ほどの凄惨ないじめはなかったが、しかし明らかに類似した状況は存在していた。今の時代に生まれていたなら、間違いなく不登校になっていただろう。
大津市のいじめ事件で怒っている人たちには、いちど内藤さんの指摘に耳を傾けてほしい。学校でいじめが起こる仕組みはすでに解明されている。事件の細部にこだわり、馬鹿の一つ覚えのように「原因の究明」「再発の防止」「命を大事にする教育」といっているだけではいじめをなくすことはできない。人は誰でも攻撃性を秘めている。それを肯定したうえで、いじめが起きるメカニズムをみんなが理解しなければいじめの解決にはつながらない。
いじめを受けている子どもたちには「いじめられるような学校なんか行くな!」と言いたい。学校の外の世界で、自分らしさを取り戻してほしいと思う。今の学校制度では、教師までもが平然と加害者になり、被害者は身も心もボロボロにされる。集団から出るしかいじめから逃れる道はないのではないか。
以下は内藤朝雄さんのブログ記事だ。なぜいじめが起きるのか、簡潔に指摘されている。ここで語られている「監禁部屋」の些末な工夫は、今の学校でのいじめ対策そのものではないか。
いじめの直し方
世の中には様々な考えの人がいて、みんな違う。「みんななかよし」なんてあり得ないのだ。個性や価値観の尊重ができる社会の構築を私たちは目指すべきだろう。
そしてつくづく思うのは、学校でのいじめと原発事故は同根であり「ムラ社会」に起因するということ。内藤さんもそのことを指摘している。この国ではどこに行っても「ムラ」があり、人の命よりムラの仲間うちの都合が優先されるのだ。根本的なところでの変革が必要だろう。
「原子力ムラ」と仲間内の論理
学校での凄惨ないじめは今にはじまったことではない。いじめが社会問題として深刻化するようになってからいったい何年が経ったのだろう。事件が明るみになる度に「原因の究明」「再発の防止」が叫ばれているが、一向に改善の兆しは見られない。言葉ばかりが空回りしているようで虚しい。悲惨な事件が報道されるたびに、多くの人が加害者や教育関係者に怒りをあらわにしているのだが、そこにも解決の糸口を見つけることはできない。
いじめのメカニズムを解き明かし、いじめ解決への提言を行っているのが社会学者の内藤朝雄氏だ。内藤氏は「いじめの社会理論」(柏書房)という本のまえがきで以下のように述べている。
大人たちは「子ども」のいじめを懸命に語ることで、実は自分たちのみじめさを語っているのかもしれない。私たちの社会では(国家権力ではなく)中間集団が非常にきつい。そこでは「人間関係をしくじると運命がどうころぶかわからない」のである。この社会の少なくとも半面は、不偏的なルールが通用しない有力者の「縁」や「みんなのムード」を頼らなければ生活の基盤が成り立たないようにできている。会社や学校では、精神的な売春とでもいうべき「なかよしごっこ」が身分関係と織り合わされて強いられる。そしてこの生きていくための日々の「屈従業務」が、人々の市民的自由と人格権を奪っている。
大人たちは、このような「世間」で卑屈にならざるを得ない屈辱を、圧倒的な集団力にさらされている「子ども」に投影し、安全な距離から「不当な仕打ち」に怒っている。
内藤氏は本書でいじめが生じる仕組みを非常に明確に解き明かしている。いじめがおきる原因は、加害者や被害者、教育関係者といった個々の人たちの問題ではない。集団の心理に起因するのであり、学校だけではなくどこでも起こりうるという指摘は非常に納得のいくものだ。学校や社会で強いられる「なかよしごっこ」、「屈従関係」が人々の自由と人格権を奪っているというのは、まさにその通りだろう。
内藤氏は、学校という共同体では以下のような状況が生じるという。
①自分の好みの生のスタイルを共通善の玉座にすえるための陰惨な殲滅戦。
②主流派になれなかった場合には、自分の目からは醜悪としか思えない共通善への屈従(へつらいの人生)を生きなければならない苦しみ。さらには、
③「われわれの特定の善なる共同世界を共に生きる」ために自分を嫌いになってまで、その共通善に「自発的」に悦服している「かのように」ようにおのれの人格を加工しなければならない(いわば魂の深いところからの精神的売春を強要される)屈辱と絶望。
これらのことはどこの集団にも存在しており誰もが経験しているだろう。こうした共同体による強制がいじめを生むのである。内藤氏は、いじめのない社会の構築のために、一人ひとりがそれぞれにとっての望ましい生のスタイルときずなを生きることができる「自由な社会」を提言する。このような社会では「なじめない者の存在を許す我慢(寛容)」が要求されるものの、「なかよしごっこ」をしない権利が保障されるのだ。
ただし、このような社会は放っておけばできるというものではない。社会的な基盤が必要だ。こうした社会の実現のために以下の要件をあげている。
①人々を狭い閉鎖空間に囲い込むマクロ条件を変えて、生活圏の規模と流動性を拡大すること。
②公私を峻別し、こころや態度を問題にしない、客観的で不偏的なルールによる支配。
そして、現行の強制的に集団生活を課す義務教育を廃止し、あらたな学習体系による教育制度を提言する。いじめ大国、自殺大国になってしまった日本において、熟考されるべき提言だろう。
思い返せば、私も学校は大嫌いだった。学校には主流派による無言の強制があり、そこから外れてしまえば非難の視線があった。でも私はたいてい主流派の中にはいなかった。だから本当の気持ちを心の奥底にしまい、いつも不満を抱えていた。自分を殺して協調性を重んじるなんてまっぴらだったし、人の顔色ばかりうかがっている人が嘘っぽく見えた。何よりも集団に拘束されず自由な自分でいられる休日が楽しみで、解放感にひたれる夏休みを待ち焦がれていた。
内藤さんの本を読むと、学校が大嫌いだった理由がストンと胸に落ちるのだ。私が学校に通っていた頃は今ほどの凄惨ないじめはなかったが、しかし明らかに類似した状況は存在していた。今の時代に生まれていたなら、間違いなく不登校になっていただろう。
大津市のいじめ事件で怒っている人たちには、いちど内藤さんの指摘に耳を傾けてほしい。学校でいじめが起こる仕組みはすでに解明されている。事件の細部にこだわり、馬鹿の一つ覚えのように「原因の究明」「再発の防止」「命を大事にする教育」といっているだけではいじめをなくすことはできない。人は誰でも攻撃性を秘めている。それを肯定したうえで、いじめが起きるメカニズムをみんなが理解しなければいじめの解決にはつながらない。
いじめを受けている子どもたちには「いじめられるような学校なんか行くな!」と言いたい。学校の外の世界で、自分らしさを取り戻してほしいと思う。今の学校制度では、教師までもが平然と加害者になり、被害者は身も心もボロボロにされる。集団から出るしかいじめから逃れる道はないのではないか。
以下は内藤朝雄さんのブログ記事だ。なぜいじめが起きるのか、簡潔に指摘されている。ここで語られている「監禁部屋」の些末な工夫は、今の学校でのいじめ対策そのものではないか。
いじめの直し方
世の中には様々な考えの人がいて、みんな違う。「みんななかよし」なんてあり得ないのだ。個性や価値観の尊重ができる社会の構築を私たちは目指すべきだろう。
そしてつくづく思うのは、学校でのいじめと原発事故は同根であり「ムラ社会」に起因するということ。内藤さんもそのことを指摘している。この国ではどこに行っても「ムラ」があり、人の命よりムラの仲間うちの都合が優先されるのだ。根本的なところでの変革が必要だろう。
「原子力ムラ」と仲間内の論理
2012年04月08日
日の丸・君が代の強制問題に思う
昨日届いた週刊金曜日に、大阪府と東京都の卒業式での不起立を貫いた教師に関する記事が掲載されていた。それによると、大阪府では「君が代」斉唱時に起立しなかった教職員は21校、29人だったそうだ。また、東京都の卒業式では3人が不起立だったとのこと。
正直いって、この程度の教師しか不起立を貫けなかったことに大きな危惧と不安を感じてしまう。
さらに驚いたのは、大阪府が行った誓約書への署名捺印だ。2月末までの卒業式で起立しなかった府立高校の17人の教師を呼び出し、起立斉唱の職務命令違反と信用失墜行為を理由とした懲戒処分の辞令を渡したという。そして、服務規律に関する30分の研修の後に「今後、入学式や卒業式における国歌斉唱時の起立斉唱を含む上司の職務命令に従います」という書面に署名捺印させたそうだ。強制ではないというものの、見せしめと強要以外の何物でもない。
「日の丸」「君が代」問題というのは、基本的に「教育現場で強制すべきことか」ということだと私は考えている。卒業式や入学式でなぜ「日の丸」を掲げ「君が代」を歌わせなければならないのだろうか? 卒業式や入学式は個々の学校の行事であり、そこで国旗を掲げたり国歌を歌う必然性など何もない。校旗や校歌で十分なはずだ。疑問はここに突き当たるのだ。
東京都のあきるの学園高等部の卒業式で不起立を貫いた田中聡史さんは、週刊金曜日で不起立の理由を以下のように語っている。
「一つには、大阪の教師も悩んで闘っているので、東京での不起立をゼロにできない気持ちから。また、教育の場で強制はあってはならない。そういう現実を不起立を通して、生徒に見せたい気持ちもあります」
強制を人権問題と捉えているのだが、憲法で保障された思想・良心の自由からすれば当然のことだろう。日の丸・君が代を強制し、従わない教師を処分するという行為自体が憲法違反だと私は思っている。だからこそ、根津君子さんも自分の良心に従って不起立を貫き、それを処分する東京都と闘っているのだ。
私が小学校に入ったときも入学式や卒業式では君が代の斉唱があった。歌うのが当たり前だったので何の疑問も持たずに歌っていたが、考えてみれば歌詞の意味を教えてもらったことなど一度もない。何も分からないまま、強制的に歌わされていたのだ。「君が代」の「君」が天皇を指すと知ったのは高校生の頃だったろうか。国歌が天皇の歌であることに違和感をもったのは言うまでもない。
「日の丸」も「君が代」も、戦争を経験してきた人たちにとっては苦い思いしかないだろう。当時の人たちの大半は、まさに「お国のため」という大義名分によって戦争に行ったのだ。そして何の罪もない人々が殺人に加担し命を落とした。その国民のマインドコントロールに使われたのが「日の丸」「君が代」である。
このような「日の丸」「君が代」を国旗・国歌とすることに反感を持っている人が少なくないのは当然だ。血塗られた歴史を背負っているなら、一部の国民の賛同を得られないなら、国旗だって国歌だって変えればいいではないか。ところが、そういう国民的議論もなしに、国旗・国歌が決められてしまった。そして、教育現場での強制である。不起立はそれに対する教師の意思表示なのだが、懲戒処分によってそれが踏み絵となっているのが現状だ。処分は「思想・良心の自由」に基づいて強制に従わない教師への見せしめなのだ。こんなおかしなことがあっていいのだろうか? ところが、そんないわれのない処分に毅然として対峙する教師の何と少ないことか。ここに大きな危惧と不安を感じるのである。
教育現場というのは思想・良心の自由をもっとも重んじなければならないところだ。そして、はじめに書いたように卒業式や入学式といった学校行事に「日の丸」や「君が代」を持ち出す必然性は何もない。ならば何のために処分という見せしめまでして「日の丸」「君が代」の強制をするのだろう。
作家の辺見庸氏が何度も繰り返しているように、この国はひそかに「戦争ができる国」へと法律を変えてきている。それと並行して教育現場への「日の丸」「君が代」の強制が強まってきている。これは無関係ではないはずだ。
私は小学校で歌わされた「君が代」に何ら抵抗感も持たなかったし歌詞の意味も知らなかったと書いた。つまり、何もわからない子どもであるが故に国旗と国歌を教育現場で刷りこみたいのだろう。独裁者が国民を支配するためには国民をマインドコントロールし、独裁者に従うように仕向けなければならない。また戦争をするためには兵士となる若い人たちを支配する構図をつくらなければならない。国民への「刷り込み」や「騙し」が必要になる。「日の丸」も「君が代」も、「お国のため」という大義名分を刷り込ませるためには大きな意味をもってくるのだ。さらに不起立の教師を処分することで、子供たちに「決まったことに逆らってはいけない」と教え込むことになる。
太平洋戦争が終わったあと、学校では教科書に墨を塗らせた。今まで教えたことが間違いであったと子どもたちに教えねばならなくなったのだ。二度とこんな矛盾した教育を行うことがあってはならない。教え子を戦争に送ってしまったことで苦しんだ教師も少なくないはずだ。
あの戦争から私たちは何を学んだのだろう。国家に騙されてはならないことではなかったのか。あの戦争で「日の丸」「君が代」は何に使われたのだろうか? 子供たちや教師にそれらを強制することこそ、国歌の思惑があると警戒しなければならない。
だからこそ、教師は凛として自分自身の思想・良心の自由を貫いてほしいと思わざるを得ない。たとえ「日の丸」や「君が代」に違和感のない教師であっても、強制や懲戒処分という暴挙にはっきりと意思表示すべきではないかと思うのだ。
仮に教師の半数が不起立を貫いたならば、教育委員会はとても処分などしていられなくなるだろう。強制を許すか否かは教師一人ひとりの意思にかかっている。不起立を貫いた教師の真摯な想いを私たちはもっと深く考え受け止める必要があるのではなかろうか。
しかし、すでに国家の思惑すら感じ取れなくなっている教師も多いのかもしれない。非常に由々しきことだ。
正直いって、この程度の教師しか不起立を貫けなかったことに大きな危惧と不安を感じてしまう。
さらに驚いたのは、大阪府が行った誓約書への署名捺印だ。2月末までの卒業式で起立しなかった府立高校の17人の教師を呼び出し、起立斉唱の職務命令違反と信用失墜行為を理由とした懲戒処分の辞令を渡したという。そして、服務規律に関する30分の研修の後に「今後、入学式や卒業式における国歌斉唱時の起立斉唱を含む上司の職務命令に従います」という書面に署名捺印させたそうだ。強制ではないというものの、見せしめと強要以外の何物でもない。
「日の丸」「君が代」問題というのは、基本的に「教育現場で強制すべきことか」ということだと私は考えている。卒業式や入学式でなぜ「日の丸」を掲げ「君が代」を歌わせなければならないのだろうか? 卒業式や入学式は個々の学校の行事であり、そこで国旗を掲げたり国歌を歌う必然性など何もない。校旗や校歌で十分なはずだ。疑問はここに突き当たるのだ。
東京都のあきるの学園高等部の卒業式で不起立を貫いた田中聡史さんは、週刊金曜日で不起立の理由を以下のように語っている。
「一つには、大阪の教師も悩んで闘っているので、東京での不起立をゼロにできない気持ちから。また、教育の場で強制はあってはならない。そういう現実を不起立を通して、生徒に見せたい気持ちもあります」
強制を人権問題と捉えているのだが、憲法で保障された思想・良心の自由からすれば当然のことだろう。日の丸・君が代を強制し、従わない教師を処分するという行為自体が憲法違反だと私は思っている。だからこそ、根津君子さんも自分の良心に従って不起立を貫き、それを処分する東京都と闘っているのだ。
私が小学校に入ったときも入学式や卒業式では君が代の斉唱があった。歌うのが当たり前だったので何の疑問も持たずに歌っていたが、考えてみれば歌詞の意味を教えてもらったことなど一度もない。何も分からないまま、強制的に歌わされていたのだ。「君が代」の「君」が天皇を指すと知ったのは高校生の頃だったろうか。国歌が天皇の歌であることに違和感をもったのは言うまでもない。
「日の丸」も「君が代」も、戦争を経験してきた人たちにとっては苦い思いしかないだろう。当時の人たちの大半は、まさに「お国のため」という大義名分によって戦争に行ったのだ。そして何の罪もない人々が殺人に加担し命を落とした。その国民のマインドコントロールに使われたのが「日の丸」「君が代」である。
このような「日の丸」「君が代」を国旗・国歌とすることに反感を持っている人が少なくないのは当然だ。血塗られた歴史を背負っているなら、一部の国民の賛同を得られないなら、国旗だって国歌だって変えればいいではないか。ところが、そういう国民的議論もなしに、国旗・国歌が決められてしまった。そして、教育現場での強制である。不起立はそれに対する教師の意思表示なのだが、懲戒処分によってそれが踏み絵となっているのが現状だ。処分は「思想・良心の自由」に基づいて強制に従わない教師への見せしめなのだ。こんなおかしなことがあっていいのだろうか? ところが、そんないわれのない処分に毅然として対峙する教師の何と少ないことか。ここに大きな危惧と不安を感じるのである。
教育現場というのは思想・良心の自由をもっとも重んじなければならないところだ。そして、はじめに書いたように卒業式や入学式といった学校行事に「日の丸」や「君が代」を持ち出す必然性は何もない。ならば何のために処分という見せしめまでして「日の丸」「君が代」の強制をするのだろう。
作家の辺見庸氏が何度も繰り返しているように、この国はひそかに「戦争ができる国」へと法律を変えてきている。それと並行して教育現場への「日の丸」「君が代」の強制が強まってきている。これは無関係ではないはずだ。
私は小学校で歌わされた「君が代」に何ら抵抗感も持たなかったし歌詞の意味も知らなかったと書いた。つまり、何もわからない子どもであるが故に国旗と国歌を教育現場で刷りこみたいのだろう。独裁者が国民を支配するためには国民をマインドコントロールし、独裁者に従うように仕向けなければならない。また戦争をするためには兵士となる若い人たちを支配する構図をつくらなければならない。国民への「刷り込み」や「騙し」が必要になる。「日の丸」も「君が代」も、「お国のため」という大義名分を刷り込ませるためには大きな意味をもってくるのだ。さらに不起立の教師を処分することで、子供たちに「決まったことに逆らってはいけない」と教え込むことになる。
太平洋戦争が終わったあと、学校では教科書に墨を塗らせた。今まで教えたことが間違いであったと子どもたちに教えねばならなくなったのだ。二度とこんな矛盾した教育を行うことがあってはならない。教え子を戦争に送ってしまったことで苦しんだ教師も少なくないはずだ。
あの戦争から私たちは何を学んだのだろう。国家に騙されてはならないことではなかったのか。あの戦争で「日の丸」「君が代」は何に使われたのだろうか? 子供たちや教師にそれらを強制することこそ、国歌の思惑があると警戒しなければならない。
だからこそ、教師は凛として自分自身の思想・良心の自由を貫いてほしいと思わざるを得ない。たとえ「日の丸」や「君が代」に違和感のない教師であっても、強制や懲戒処分という暴挙にはっきりと意思表示すべきではないかと思うのだ。
仮に教師の半数が不起立を貫いたならば、教育委員会はとても処分などしていられなくなるだろう。強制を許すか否かは教師一人ひとりの意思にかかっている。不起立を貫いた教師の真摯な想いを私たちはもっと深く考え受け止める必要があるのではなかろうか。
しかし、すでに国家の思惑すら感じ取れなくなっている教師も多いのかもしれない。非常に由々しきことだ。
2011年03月04日
入試問題投稿事件から何を考えるべきか
ここ数日、ある予備校生が携帯電話を使ってインターネットの質問サイトに入試問題を投稿した事件がトップニュースとなっている。しかし、入試のカンニング事件をトップニュースとしてこれほどにまで大々的に報道する必要があるのだろうか? この受験生の行為はもちろんやってはならないことだが、それにしても連日大きく放送するほどのニュースとは思えない。マスコミはなぜこれほどまでに大騒ぎするのだろうか。
カンニングなどというのは昔からあったし、替え玉受験などというのもあった。しかし、そのようなことはもちろんトップニュースにはならないし、不正が発覚したなら大学が独自に調査し対応したので全国に知れ渡るような騒ぎにはならなかった。
今回の不正はインターネットを利用した特殊な方法であり、不正をした受験生を速やかに特定するためにはプロバイダにIPアドレスの提示を求める必要があったとはいえ、刑事事件にまでしなければ解決方法がなかったとは思えない。刑事事件にまで発展したことで、この受験生の今後の大学進学は極めて困難になるだろうし、ひとりの若者の将来に致命的ともいえる禍根を残してしまった。本人は深く反省しているそうだが、この騒ぎによって受けた心の傷は大きいに違いない。マスコミはあまりにも無神経だ。これを引き金に深刻な精神状態にならないことを願いたい。
今回の不正は、どうしても入学したいという単純な動機からだったようだ。彼は、こんな不正を考えるほど追いつめられていたということだろう。私は、この事件で考えるべきことはこの受験生の行為というより、大学入試のあり方だと思う。
日本では大学入試のハードルが高く、卒業のハードルはきわめて低い。このために少なくとも中学以降は入学試験をクリアするために勉強しているといっても過言ではない。試験でいい点をとることが勉強なのである。教師も生徒も入試に振り回され、人生のうちでも多感な青春時代に、クラスメートや友人との競争を強いられているのが現実だ。これでは、自ら好奇心をもって知識を吸収したり、自分で考える力を身につけるような学びはできない。
こんな状態だから、大学に入学することが目的となり、そこで何を学びたいのかがはっきりしない生徒も多い。自分の学びたい分野というより、自分の学力レベルで大学を選ぶと者も多いというから驚きだ。入試が目的になっているから、大学入学という目的を果たしてしまったら、部活動やアルバイトに忙しく学業がおろそかになる学生も少なからずいる。第三者から見たら何のために大学に行くのかと思うことすらある。大学は学びの場という以上に、就職の先延ばしとして利用されている側面もある。
入学試験以上に卒業を厳しくしたなら、おそらくこんな状況にはならないだろう。高い学費を払って大学に行っても、専門知識を活かしたり自分で物事を考え行動することもできないのであれば、何のための高等教育なのかということにもなる。
それともう一つ、学生も一流大学に入ることだけを目的にするのはやめたほうがいい。もちろん、親も自分の子どもに過剰な期待をかけるべきではない。学ぶ=一流大学に入学する、ということではない。一流大学ではなくても、すばらしい研究をしている教員、人間として優れている教員はいくらでもいるだろう。逆に、一流大学の教員がみな優れているというわけでもない。本人にやる気があれば大学の名前など関係はないし、著名な大学を卒業したからといって、将来が保障されているわけでもない。大学名で大学を選ぶというのはナンセンスだ。家庭の事情などで進学したくてもできない若者もたくさんいる。出身大学や学歴で人間を評価したり判断するのも馬鹿馬鹿しい。
カンニングなどというのは昔からあったし、替え玉受験などというのもあった。しかし、そのようなことはもちろんトップニュースにはならないし、不正が発覚したなら大学が独自に調査し対応したので全国に知れ渡るような騒ぎにはならなかった。
今回の不正はインターネットを利用した特殊な方法であり、不正をした受験生を速やかに特定するためにはプロバイダにIPアドレスの提示を求める必要があったとはいえ、刑事事件にまでしなければ解決方法がなかったとは思えない。刑事事件にまで発展したことで、この受験生の今後の大学進学は極めて困難になるだろうし、ひとりの若者の将来に致命的ともいえる禍根を残してしまった。本人は深く反省しているそうだが、この騒ぎによって受けた心の傷は大きいに違いない。マスコミはあまりにも無神経だ。これを引き金に深刻な精神状態にならないことを願いたい。
今回の不正は、どうしても入学したいという単純な動機からだったようだ。彼は、こんな不正を考えるほど追いつめられていたということだろう。私は、この事件で考えるべきことはこの受験生の行為というより、大学入試のあり方だと思う。
日本では大学入試のハードルが高く、卒業のハードルはきわめて低い。このために少なくとも中学以降は入学試験をクリアするために勉強しているといっても過言ではない。試験でいい点をとることが勉強なのである。教師も生徒も入試に振り回され、人生のうちでも多感な青春時代に、クラスメートや友人との競争を強いられているのが現実だ。これでは、自ら好奇心をもって知識を吸収したり、自分で考える力を身につけるような学びはできない。
こんな状態だから、大学に入学することが目的となり、そこで何を学びたいのかがはっきりしない生徒も多い。自分の学びたい分野というより、自分の学力レベルで大学を選ぶと者も多いというから驚きだ。入試が目的になっているから、大学入学という目的を果たしてしまったら、部活動やアルバイトに忙しく学業がおろそかになる学生も少なからずいる。第三者から見たら何のために大学に行くのかと思うことすらある。大学は学びの場という以上に、就職の先延ばしとして利用されている側面もある。
入学試験以上に卒業を厳しくしたなら、おそらくこんな状況にはならないだろう。高い学費を払って大学に行っても、専門知識を活かしたり自分で物事を考え行動することもできないのであれば、何のための高等教育なのかということにもなる。
それともう一つ、学生も一流大学に入ることだけを目的にするのはやめたほうがいい。もちろん、親も自分の子どもに過剰な期待をかけるべきではない。学ぶ=一流大学に入学する、ということではない。一流大学ではなくても、すばらしい研究をしている教員、人間として優れている教員はいくらでもいるだろう。逆に、一流大学の教員がみな優れているというわけでもない。本人にやる気があれば大学の名前など関係はないし、著名な大学を卒業したからといって、将来が保障されているわけでもない。大学名で大学を選ぶというのはナンセンスだ。家庭の事情などで進学したくてもできない若者もたくさんいる。出身大学や学歴で人間を評価したり判断するのも馬鹿馬鹿しい。
2010年02月11日
奨学金という借金を抱える学生
今日の北海道新聞に、「仕送り0学生10%超す」という記事が掲載されていました。記事によると、仕送りを受けていない下宿通学(親元を離れてアパートなどから通学)の大学生の割合が10.2%に達したとのこと。仕送り額が5万円未満の下宿生も22.7%で、毎月の仕送り額の平均は7万4060円なのだそうです。
場所にもよりますが、アパートの家賃だけでも4~5万円はするでしょうから、7万とか8万の収入では生活ができません。アルバイトや奨学金に頼らなければとてもやっていけないのが多くの下宿通いの大学生の実態です。親元から通えるところに希望の大学があればいいのですが、地方に住んでいたらどうしても下宿や寮生活にならざるを得ません。都市と地方では大きな教育格差が生じています。
私の知人で昨年息子さんがある私立大学に入学した方がいるのですが、仕送りはゼロだと言っていました。学費は親が支払っているようですが、生活費は全額アルバイトと奨学金で何とかしているそうです。4年間で何百万円も奨学金を借りることになるといいます。息子さんが入学する前にそのような話を聞き、私は正直いってかなり驚きました。「それじゃあ卒業と同時に借金地獄になるでしょ。本人はそのこと理解しているの?」と聞くと、「そういうことも計算させたから理解しているはずだし、本人の希望だから・・・」とのことでした。この話に、なんだか溜め息が出てきました。
上記の記事によると、下宿生の収入合計は12万5580円とのことですから、それ位の生活費がかかるということでしょう。アルバイトの収入が月額数万円あったとしても、仕送りがゼロならかなりの奨学金をもらわなければやっていけません。仮に年額100万円(月額約8.3万円)の奨学金を受給したら4年間で400万円にもなりますし、返済時には利息もつきます。正社員として就職できても、返済はかなりの重荷になるはず。いったい何年で返せることか。もし卒業しても就職できず、フリーター生活になれば大変なことになるのが目に見えています。この就職難の時代に、しかもまだ20代の前半から借金の返済に追われることにもなるでしょう。
私も日本育英会の奨学金をもらっていましたが、あの頃は受給金額もそれほど多くはなく、無利子でしたから返済はそれほど大変ではありませんでした。でも、今は受給金額のケタが違います。
かつてはアルバイトで生活を支えて頑張っている学生を「苦学生」といいましたが、いまはアルバイトだけではとても足りずに奨学金頼りです。しかし、20代で多額の借金を抱えてしまうような状況はとても正常とはいえません。教育制度などの改革をしないと、とんでもないことになるのではないでしょうか。
場所にもよりますが、アパートの家賃だけでも4~5万円はするでしょうから、7万とか8万の収入では生活ができません。アルバイトや奨学金に頼らなければとてもやっていけないのが多くの下宿通いの大学生の実態です。親元から通えるところに希望の大学があればいいのですが、地方に住んでいたらどうしても下宿や寮生活にならざるを得ません。都市と地方では大きな教育格差が生じています。
私の知人で昨年息子さんがある私立大学に入学した方がいるのですが、仕送りはゼロだと言っていました。学費は親が支払っているようですが、生活費は全額アルバイトと奨学金で何とかしているそうです。4年間で何百万円も奨学金を借りることになるといいます。息子さんが入学する前にそのような話を聞き、私は正直いってかなり驚きました。「それじゃあ卒業と同時に借金地獄になるでしょ。本人はそのこと理解しているの?」と聞くと、「そういうことも計算させたから理解しているはずだし、本人の希望だから・・・」とのことでした。この話に、なんだか溜め息が出てきました。
上記の記事によると、下宿生の収入合計は12万5580円とのことですから、それ位の生活費がかかるということでしょう。アルバイトの収入が月額数万円あったとしても、仕送りがゼロならかなりの奨学金をもらわなければやっていけません。仮に年額100万円(月額約8.3万円)の奨学金を受給したら4年間で400万円にもなりますし、返済時には利息もつきます。正社員として就職できても、返済はかなりの重荷になるはず。いったい何年で返せることか。もし卒業しても就職できず、フリーター生活になれば大変なことになるのが目に見えています。この就職難の時代に、しかもまだ20代の前半から借金の返済に追われることにもなるでしょう。
私も日本育英会の奨学金をもらっていましたが、あの頃は受給金額もそれほど多くはなく、無利子でしたから返済はそれほど大変ではありませんでした。でも、今は受給金額のケタが違います。
かつてはアルバイトで生活を支えて頑張っている学生を「苦学生」といいましたが、いまはアルバイトだけではとても足りずに奨学金頼りです。しかし、20代で多額の借金を抱えてしまうような状況はとても正常とはいえません。教育制度などの改革をしないと、とんでもないことになるのではないでしょうか。
タグ :奨学金
2010年01月31日
言語力低下の背景にあるもの
昨日のNHKテレビの「A to Z」では、「“言語力”を磨け」とのテーマで、日本の若者の言語力が著しく低下していることについて取り上げていました。自分の考えや意見を主張できなかったり、論理的な文章を書けない若者が非常に増えており、言語力を鍛える教育をしている企業もあるそうです。その背景には、以下のようなことがあると指摘していました。
学校で、自分の考えを発表するような教育を行っていない。試験にしてもマークシート方式で複数の選択肢の中から選ぶだけであり、論理立てて文章を書くという訓練がなされていない。また、携帯メールでのやりとりが日常的になっている若者は、小さい画面で読める必要最小限の短い文章しか書かない。日本人はとりわけ以心伝心といったことを大事にし、自己主張することは敬遠されてきたが、グローバル化した情報社会では「以心伝心」に頼っていたのでは主張が伝わらず歪が生じる
そのような指摘はもっともでしょう。しかし、この番組では重要なことが語られていないと感じました。まず、子どもたちの間に定着してしまった「空気を読んで、周りに合わせる」という行動パターンです。週刊金曜日に青木悦さんによる「しんどいなあ」という連載が掲載されていましたが、2009年12月11日号に驚くような事例が紹介されていました。
中学一年生のある女の子が、クラスの女子全員に「今日はごめんね、ごめんね」と言って謝って回っているというのです、なぜかと聞くと、「授業中、すごく目立つ発言をしちゃったの」とのこと。彼女曰く「いいか悪いかじゃなくてエ、とにかく今日中にイ、私がそのことを悪かったと気づいて謝っておくことが大事なのオ。そうじゃないとオ、今夜中にメールがまわってエ、明日の朝学校に行ったらみんなでシカト、なんて、あるのオ」
「みんなと同じ」からはみ出てしまったなら、孤立していじめられるしかないのです。周囲の人たちに合わせ「空気を読む」ことに必死になっている現代の子どもたちの姿が浮かび上がってきます。子どもたちの間には「周りに合わせていなければいけない」「目立ったことをしてはいけない」ということが理屈抜きに無意識に浸透しています。いじめられたり仲間外れにされないために、ここまでピリピリして気を使っているのが現実であれば、「自分の考えを言う」「他人と違うことを言う」ことなどトンデモナイことでありタブーでしょう。
これは、以心伝心などという以前の問題であり、恐るべき状況です。しかし、今の子どもたちの置かれたこうした状況を、中高年以上の年齢層の多くが理解していないと思います。ここ数十年で、子どもたちを取り巻く環境は激変しています。「空気を読む」ことにがんじがらめにされている状況を把握し正面から取り組まない限り、いくら授業で「自分の意見を言う」ことを取り入れても、それを子どもたちの日常生活に根づかせることは困難でしょう。もっとも、子どもたちをこのような状況に陥らせたのは、周囲の大人の責任でもあるのですが。
学校でのいじめや仲間外れが社会問題になってから久しいのに、日本ではいじめに対する取り組みがあまりにもおざなりにされています。携帯メールなどの普及がそれに拍車をかけています。若者の言語力の低下の問題はここから論じなければならないでしょう。
言語力の低下で、もうひとつ指摘しなければならないのは、読書量の低下です。10年以上前のことですが、娘の中学校に行ったとき、図書室に鍵がかけられているのを見て驚きました。子どもたちに本を読む機会を与えるべき図書室が、その役割を放棄しているのです。しかも、子どもたちは部活、部活に追われる毎日で、授業が終わって部活に参加したらそれだけでクタクタです。しばしば休日にも部活に出かけます。さらに多くの子どもが塾や習い事を抱えています。これでは読書どころではありません。大半の子どもがろくに本を読まない生活をしているのではないでしょうか。
読書好きの子どもは、自然と論理的な文章が書けるようになるものですが、現代の子どもたちは読書する時間もありません。「みんなに合わせる」ことで精神的に消耗し、部活や塾通いでクタクタになり、読書を楽しむ時間もないような毎日を過ごしていたら、言語力の低下が起きるのは当たり前です。子どもの生活にゆとりを与えることから考えなければならないことです。
学校で、自分の考えを発表するような教育を行っていない。試験にしてもマークシート方式で複数の選択肢の中から選ぶだけであり、論理立てて文章を書くという訓練がなされていない。また、携帯メールでのやりとりが日常的になっている若者は、小さい画面で読める必要最小限の短い文章しか書かない。日本人はとりわけ以心伝心といったことを大事にし、自己主張することは敬遠されてきたが、グローバル化した情報社会では「以心伝心」に頼っていたのでは主張が伝わらず歪が生じる
そのような指摘はもっともでしょう。しかし、この番組では重要なことが語られていないと感じました。まず、子どもたちの間に定着してしまった「空気を読んで、周りに合わせる」という行動パターンです。週刊金曜日に青木悦さんによる「しんどいなあ」という連載が掲載されていましたが、2009年12月11日号に驚くような事例が紹介されていました。
中学一年生のある女の子が、クラスの女子全員に「今日はごめんね、ごめんね」と言って謝って回っているというのです、なぜかと聞くと、「授業中、すごく目立つ発言をしちゃったの」とのこと。彼女曰く「いいか悪いかじゃなくてエ、とにかく今日中にイ、私がそのことを悪かったと気づいて謝っておくことが大事なのオ。そうじゃないとオ、今夜中にメールがまわってエ、明日の朝学校に行ったらみんなでシカト、なんて、あるのオ」
「みんなと同じ」からはみ出てしまったなら、孤立していじめられるしかないのです。周囲の人たちに合わせ「空気を読む」ことに必死になっている現代の子どもたちの姿が浮かび上がってきます。子どもたちの間には「周りに合わせていなければいけない」「目立ったことをしてはいけない」ということが理屈抜きに無意識に浸透しています。いじめられたり仲間外れにされないために、ここまでピリピリして気を使っているのが現実であれば、「自分の考えを言う」「他人と違うことを言う」ことなどトンデモナイことでありタブーでしょう。
これは、以心伝心などという以前の問題であり、恐るべき状況です。しかし、今の子どもたちの置かれたこうした状況を、中高年以上の年齢層の多くが理解していないと思います。ここ数十年で、子どもたちを取り巻く環境は激変しています。「空気を読む」ことにがんじがらめにされている状況を把握し正面から取り組まない限り、いくら授業で「自分の意見を言う」ことを取り入れても、それを子どもたちの日常生活に根づかせることは困難でしょう。もっとも、子どもたちをこのような状況に陥らせたのは、周囲の大人の責任でもあるのですが。
学校でのいじめや仲間外れが社会問題になってから久しいのに、日本ではいじめに対する取り組みがあまりにもおざなりにされています。携帯メールなどの普及がそれに拍車をかけています。若者の言語力の低下の問題はここから論じなければならないでしょう。
言語力の低下で、もうひとつ指摘しなければならないのは、読書量の低下です。10年以上前のことですが、娘の中学校に行ったとき、図書室に鍵がかけられているのを見て驚きました。子どもたちに本を読む機会を与えるべき図書室が、その役割を放棄しているのです。しかも、子どもたちは部活、部活に追われる毎日で、授業が終わって部活に参加したらそれだけでクタクタです。しばしば休日にも部活に出かけます。さらに多くの子どもが塾や習い事を抱えています。これでは読書どころではありません。大半の子どもがろくに本を読まない生活をしているのではないでしょうか。
読書好きの子どもは、自然と論理的な文章が書けるようになるものですが、現代の子どもたちは読書する時間もありません。「みんなに合わせる」ことで精神的に消耗し、部活や塾通いでクタクタになり、読書を楽しむ時間もないような毎日を過ごしていたら、言語力の低下が起きるのは当たり前です。子どもの生活にゆとりを与えることから考えなければならないことです。
2008年10月19日
子どもたちは今…
ちょっと古い本ですが、先日「負けるな子どもたち!」(渡辺容子著、径書房)を読み、すさんできている子どもたちと教育環境について考えさせられました。著者の渡辺容子さんは、都内の学童保育の指導員をされていた方です。
私自身、自分の子育ての過程で子どもたちや学校がずいぶん変わってきていることを感じてはいました。自分の子ども時代と比較してみると何かが違う、子どもも学校も変わってしまった… そんな気持ちを強く抱いてはいたものの、いまひとつ実感として捉えられないでいました。しかし、学童保育の指導員として子どもたちと関り、その様子を伝えるこの本を読んで、目からウロコのように子どもたちの変貌を感じとることができました。
渡辺さんは、子どもたちの心がすさんでしまったこと、変わってしまったことに悩まされます。塾や習い事に追われる子どもたち。落ち着きなく言葉を荒げ、すぐに暴力をふるい平然といじめをする子どもたち。吹き荒れる嵐のような子どもたちの中に入り込んで彼らを受け止め、寄り添い理解しようとする行動には心が打たれます。
私は渡辺さんと同世代です。私の子ども時代にも塾や習い事はありましたし、いじめもありました。でも、どうやらそれらの質や中身は驚くほど変わってしまったようです。放課後は家にランドセルを放り出して遊びまわりましたし、夏休みなども実に自由に過したものです。いじめといっても陰湿さはありませんでしたし、ごく一部の子どもの問題でした。個性の強い子どもも、それなりに認められるところがあったのです。でもほんの2,30年の間にすっかり状況が変わってしまったようです。もちろんそれは子どもたちに原因があるのではなく、社会の問題です。
今の若い人(あまり使いたくない言葉ですが)を見ていると、驚くほど周囲の評価を気にして周りに合わせようとしている人が少なくありません。そうするように強いている社会があるのです。子どものころから競争に駆り立てられ、いじめられることを恐れ、身も心も疲れてストレスをため、追い詰められているのです。それは子どもたちだけではありません。この国は何もかも大変な状況になりつつあります。
この本のなかで、フィリピンの小さな島の子どもたちのことが紹介されています。文房具もなく着る物さえも不自由する生活であっても、いきいきとして表情の豊かな子どもたち。家の仕事を当たり前のようにこなし、礼儀をわきまえた子どもたち。開発途上といわれている国の子どもたちは皆同じでしょう。そして、同じような姿は少し前の日本にもあったはずです。
物質的な豊かさと裏腹に、私たちは大切なものを失ってきました。もちろん、昔の不便な生活に戻すべきだなどとはいいません。しかし、本当にこれでいいのでしょうか? 暗澹たる気持ちになります。でも打ちひしがれているだけでなく、なぜこうなったのかを問いただし変える努力をすることこそしていかなければならないでしょう。
今は学童保育の仕事を離れたものの、一市民として地道に努力を続けている渡辺さんに、エールを送ります。
私自身、自分の子育ての過程で子どもたちや学校がずいぶん変わってきていることを感じてはいました。自分の子ども時代と比較してみると何かが違う、子どもも学校も変わってしまった… そんな気持ちを強く抱いてはいたものの、いまひとつ実感として捉えられないでいました。しかし、学童保育の指導員として子どもたちと関り、その様子を伝えるこの本を読んで、目からウロコのように子どもたちの変貌を感じとることができました。
渡辺さんは、子どもたちの心がすさんでしまったこと、変わってしまったことに悩まされます。塾や習い事に追われる子どもたち。落ち着きなく言葉を荒げ、すぐに暴力をふるい平然といじめをする子どもたち。吹き荒れる嵐のような子どもたちの中に入り込んで彼らを受け止め、寄り添い理解しようとする行動には心が打たれます。
私は渡辺さんと同世代です。私の子ども時代にも塾や習い事はありましたし、いじめもありました。でも、どうやらそれらの質や中身は驚くほど変わってしまったようです。放課後は家にランドセルを放り出して遊びまわりましたし、夏休みなども実に自由に過したものです。いじめといっても陰湿さはありませんでしたし、ごく一部の子どもの問題でした。個性の強い子どもも、それなりに認められるところがあったのです。でもほんの2,30年の間にすっかり状況が変わってしまったようです。もちろんそれは子どもたちに原因があるのではなく、社会の問題です。
今の若い人(あまり使いたくない言葉ですが)を見ていると、驚くほど周囲の評価を気にして周りに合わせようとしている人が少なくありません。そうするように強いている社会があるのです。子どものころから競争に駆り立てられ、いじめられることを恐れ、身も心も疲れてストレスをため、追い詰められているのです。それは子どもたちだけではありません。この国は何もかも大変な状況になりつつあります。
この本のなかで、フィリピンの小さな島の子どもたちのことが紹介されています。文房具もなく着る物さえも不自由する生活であっても、いきいきとして表情の豊かな子どもたち。家の仕事を当たり前のようにこなし、礼儀をわきまえた子どもたち。開発途上といわれている国の子どもたちは皆同じでしょう。そして、同じような姿は少し前の日本にもあったはずです。
物質的な豊かさと裏腹に、私たちは大切なものを失ってきました。もちろん、昔の不便な生活に戻すべきだなどとはいいません。しかし、本当にこれでいいのでしょうか? 暗澹たる気持ちになります。でも打ちひしがれているだけでなく、なぜこうなったのかを問いただし変える努力をすることこそしていかなければならないでしょう。
今は学童保育の仕事を離れたものの、一市民として地道に努力を続けている渡辺さんに、エールを送ります。
2008年09月27日
大学院は何のためにあるのか?
私が学生だったころは、大学院に進学する人はごく一部の研究者を目指す人たちでした。それだけ大学院は狭き門でしたし、研究志向の強い人しか行かなかったのです。
ところが、いつ頃からだったでしょうか、知り合いの学生さんなどで大学院に進学する人たちがどんどん増えていったのです。研究職を強く希望する人ならわかりますが、必ずしもそうではなさそうなのですね。
大学を卒業しても就職がないという理由の人も多かったようです。就職先がないから、とりあえず進学するというわけです。就職の先延ばしですね。すると、どうしても研究に熱心ではない学生さんも出てきます。大学院生の質の低下が起こるのです。
その背景には就職氷河期だけではなく、大学院生の定員の増加があります。先日ある大学の先生から聞いた話しですが、国立大学では10年ほど前に大学院の定員を3倍にしたそうです。これによって、それまでよりも大学院への進学が容易になりました。どおりで誰もが気軽に大学院に進学するわけですね。最近ではやる気のない学生が増えて、教員は指導が大変なのだそうなのです。大学生ではなくて、大学院生がですよ。
ところが大学の教員採用の方はどうしたかというと、増やすどころか半分にしたというのです。博士号を取得したものの、就職できない人が溢れるようになってしまいました。
あまりにも当然のことですが、なぜこんなことをしたのでしょうか? 私にはお金儲けとしか思えません。学費集めです。大学院生を増やして収入を増加させることが最大の目的であり、卒業後の就職などどうでもいいということではないでしょうか。入学だけさせておいて、あとは勝手にしろというわけですね。でも、高学歴になるほど就職は難しいのです。
このような国のやり方は、まるで大学院を利用した詐欺的行為です。学生を「歩く札束」だとでも思っているのでしょうか。
今は国立大学に限らず、あちこちの大学に大学院が設置されています。でも、卒業したところで就職先は保証されていません。大学院で優秀な研究をしても就職口がなく、研究生活を断念せざるを得ない人も多いことでしょう。これでは優秀な人材も散逸してしまいます。
いったい何のための大学院なのでしょうか? この国の歪みは大学院にまで及んでいるようです。
ところが、いつ頃からだったでしょうか、知り合いの学生さんなどで大学院に進学する人たちがどんどん増えていったのです。研究職を強く希望する人ならわかりますが、必ずしもそうではなさそうなのですね。
大学を卒業しても就職がないという理由の人も多かったようです。就職先がないから、とりあえず進学するというわけです。就職の先延ばしですね。すると、どうしても研究に熱心ではない学生さんも出てきます。大学院生の質の低下が起こるのです。
その背景には就職氷河期だけではなく、大学院生の定員の増加があります。先日ある大学の先生から聞いた話しですが、国立大学では10年ほど前に大学院の定員を3倍にしたそうです。これによって、それまでよりも大学院への進学が容易になりました。どおりで誰もが気軽に大学院に進学するわけですね。最近ではやる気のない学生が増えて、教員は指導が大変なのだそうなのです。大学生ではなくて、大学院生がですよ。
ところが大学の教員採用の方はどうしたかというと、増やすどころか半分にしたというのです。博士号を取得したものの、就職できない人が溢れるようになってしまいました。
あまりにも当然のことですが、なぜこんなことをしたのでしょうか? 私にはお金儲けとしか思えません。学費集めです。大学院生を増やして収入を増加させることが最大の目的であり、卒業後の就職などどうでもいいということではないでしょうか。入学だけさせておいて、あとは勝手にしろというわけですね。でも、高学歴になるほど就職は難しいのです。
このような国のやり方は、まるで大学院を利用した詐欺的行為です。学生を「歩く札束」だとでも思っているのでしょうか。
今は国立大学に限らず、あちこちの大学に大学院が設置されています。でも、卒業したところで就職先は保証されていません。大学院で優秀な研究をしても就職口がなく、研究生活を断念せざるを得ない人も多いことでしょう。これでは優秀な人材も散逸してしまいます。
いったい何のための大学院なのでしょうか? この国の歪みは大学院にまで及んでいるようです。