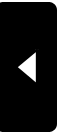鬼蜘蛛の網の片隅から
2025年05月08日
シロクビキリガ
灰褐色のキリガで、前翅の付け根が淡色で目立ち、腎状紋の中は赤褐色になる。がっしりとした感じでなかなか格好いい。秋に出現して成虫越冬し春まで見られるそうだ。前翅長は20mmくらい。ヤガ科キリガ亜科。

2020年10月30日 北海道十勝地方
2020年10月30日 北海道十勝地方
2025年05月07日
ヌカビラネジロキリガ
全体に灰色味が強いモノトーンのキリガで、日本では北海道に局地的(主に道東)に分布する。幼虫の食餌植物は不明だが、ヨーロッパではヤナギ類を食べるとのこと。前翅長は13mmくらい。ヤガ科キリガ亜科。

2024年7月23日 北海道十勝地方

2024年7月23日 北海道十勝地方
2025年05月06日
2025年05月05日
ショウブヨトウの一種
ショウブヨトウ、タカネショウブヨトウ、キタショウブヨトウ、エゾショウブヨトウはどれも斑紋がよく似ていて外見では区別できないため、ショウブヨトウの一種とした。腎状紋が白くなるものもいる。幼虫はイネ科植物を食べる。写真の個体は前翅長15mm。ヤガ科キリガ亜科。

2024年7月27日 北海道十勝地方
2024年7月27日 北海道十勝地方
2025年05月04日
ギシギシヨトウ
地味な蛾だが、新鮮な個体だと内横線の内側や外横線外側の後縁付近が緑がかっている。ギシギシとついているのでタデ科植物を食べるのかと思いきや、幼虫の食草はイネ科植物とのこと。前翅長は18mmくらい。ヤガ科キリガ亜科。

2024年7月31日 北海道十勝地方
2024年7月31日 北海道十勝地方
2025年05月03日
看過できないマイクロ・ナノプラスチック問題
プラスチックごみを大量に排出するようになってだいぶ経ってから、マイクロプラスチック(5mm未満)やナノプラスチック(100nm未満)問題が浮上してきた。海などの汚染だけではなく、食べ物や飲み物などから人体にも多量のマイクロプラスチックが取り込まれている。
体内に取り込まれたマイクルプラスチックは臓器に蓄積され、血流にのって脳にまで到達する。消化器系、免疫系、神経系、内分泌系などへの悪影響が懸念される。詳しくは以下参照。
マイクロプラスチック問題と人体への影響|今すぐ始める効果的対策
また、最近の研究では、胎盤を通過して代謝ストレスを引き起こし、長期的な健康被害を及ぼすことが懸念されている。
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40066256/
私は口から入るマイクロ・ナノプラスチックとして、とりわけティーバックを懸念している。ティーバックから出るマイクロ・ナノプラスチックはティーバックの素材によっても違うので一概には言えないが、多量のマイクロ・ナノプラスチックが溶け出すことは間違いない。こちらの記事によると、一袋で約116億個のマイクロプラスチック、約31億個のナノプラスチックが溶け出ているという。お茶を一杯飲むだけで大量のマイクロ・ナノプラスチックを体内に取り込むことになる。
こういうことが分かってきているのに、ティーバックは一向に減らない。私は紅茶はティーバックをやめ、ステンレスの茶こしがついたポットで淹れるようにした。ティーバック入りしか売っていないものは、バックから中身を出して茶こしに移して淹れている。
それから、日常的なマイクロ・ナノプラスチックの取り込みとして、フッ素加工のフライパンも気になっている。ネットでフライパンのフッ素樹脂加工について調べると、使い方さえ守れば問題ないという記事が複数出てくるが、私は全く信用していない。このような記事は恐らくメーカーなどが書いているのだろう。フッ素樹脂加工のフライパンは、適切な使い方をしていても次第にコーティングがはがれて食材がくっつくようになる。そのはがれたフッ素樹脂はマイクロプラスチックになる。もちろん、フッ素の毒性のことも問題だ(こちら参照)。
私は鉄のフライパンをメインに使っているが、少し大きめのフライパンが欲しくてホームセンターを3店回ったことがある。しかし、どこのフライパン売り場もフッ素樹脂加工のフライパンばかり。鉄のフライパンは小さめのものが一種類くらいあるだけでほしいサイズがなく、結局、通販で買った。フッ素やマイクロプラスチックの問題が指摘されているのに、鉄のフライパンが少ないことに驚いた。フッ素樹脂加工のフライパンが数年で劣化することを考えたら、多少値段が高くても何十年も使える鉄のフライパンの方がずっといい。
ということで、国が規制しないなら、自分で気を付けるしかない。
体内に取り込まれたマイクルプラスチックは臓器に蓄積され、血流にのって脳にまで到達する。消化器系、免疫系、神経系、内分泌系などへの悪影響が懸念される。詳しくは以下参照。
マイクロプラスチック問題と人体への影響|今すぐ始める効果的対策
また、最近の研究では、胎盤を通過して代謝ストレスを引き起こし、長期的な健康被害を及ぼすことが懸念されている。
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40066256/
私は口から入るマイクロ・ナノプラスチックとして、とりわけティーバックを懸念している。ティーバックから出るマイクロ・ナノプラスチックはティーバックの素材によっても違うので一概には言えないが、多量のマイクロ・ナノプラスチックが溶け出すことは間違いない。こちらの記事によると、一袋で約116億個のマイクロプラスチック、約31億個のナノプラスチックが溶け出ているという。お茶を一杯飲むだけで大量のマイクロ・ナノプラスチックを体内に取り込むことになる。
こういうことが分かってきているのに、ティーバックは一向に減らない。私は紅茶はティーバックをやめ、ステンレスの茶こしがついたポットで淹れるようにした。ティーバック入りしか売っていないものは、バックから中身を出して茶こしに移して淹れている。
それから、日常的なマイクロ・ナノプラスチックの取り込みとして、フッ素加工のフライパンも気になっている。ネットでフライパンのフッ素樹脂加工について調べると、使い方さえ守れば問題ないという記事が複数出てくるが、私は全く信用していない。このような記事は恐らくメーカーなどが書いているのだろう。フッ素樹脂加工のフライパンは、適切な使い方をしていても次第にコーティングがはがれて食材がくっつくようになる。そのはがれたフッ素樹脂はマイクロプラスチックになる。もちろん、フッ素の毒性のことも問題だ(こちら参照)。
私は鉄のフライパンをメインに使っているが、少し大きめのフライパンが欲しくてホームセンターを3店回ったことがある。しかし、どこのフライパン売り場もフッ素樹脂加工のフライパンばかり。鉄のフライパンは小さめのものが一種類くらいあるだけでほしいサイズがなく、結局、通販で買った。フッ素やマイクロプラスチックの問題が指摘されているのに、鉄のフライパンが少ないことに驚いた。フッ素樹脂加工のフライパンが数年で劣化することを考えたら、多少値段が高くても何十年も使える鉄のフライパンの方がずっといい。
ということで、国が規制しないなら、自分で気を付けるしかない。
2025年05月02日
サッポロチャイロヨトウ
この仲間は似たようなものが多い上に、色彩などの変異が大きい種もあるのでいつも同定に悩まされるのだが、サッポロチャイロヨトウと同定。間違っていたら教えてほしい。幼虫はササの葉を食べるとのこと。写真の個体は前翅長約18mm。ヤガ科キリガ亜科。

2024年7月12日 北海道十勝地方

2024年7月12日 北海道十勝地方
2025年05月01日
百日咳ワクチンは必要か?
北海道新聞に百日咳のワクチンを推奨する記事が出ていた。妊婦にまで推奨している。
百日ぜき道内で拡大 乳児は重症化の傾向 専門家「妊娠中のワクチン接種を」
昨今は感染症が流行ればすぐにワクチンを推奨する。新聞がこんな記事を出せば、ワクチンの追加接種をしようと思う人も増えるだろう。しかし、マスコミの推奨記事は、ワクチンの負の側面についてほとんど触れていない。
そこで、「ワクチン神話捏造の歴史」(ヒカルランド)から、百日咳ワクチンについて指摘されている問題点について箇条書きにして紹介しておきたい。
・19世紀に百日咳の死者はピークを迎え、百日咳ワクチンが使用される前にすでに99%以上死亡者が減少していた。
・現在の百日咳は以前より致死率が低下し、深刻な病気ではなくなった。
・百日咳ワクチンの接種により、急性脳症状や神経系の障害が生じることがあり、死亡することもある。
・ワクチンを接種した人は、5~10年後には百日咳に罹りやすくなる。
・乳児と幼児に投与される百日咳ワクチンは、3年後に有効性を失う。
・百日咳はワクチン接種率の高い集団において流行する病気。
・ワクチン接種者かどうかにかかわらず、保菌して伝播するのを防ぐ効果はないし、無症状感染者も多い。
・百日咳菌のワクチン耐性が生じている。
百日咳はワクチンを打つようになっても根絶されていない。子どもだけではなく大人も感染するし、無症状の場合も多い。ワクチンを打たずに自然感染した方が免疫は長持ちする一方で、接種者は抗原原罪により感染を拡大させるようだ。これらのリスクを考え合わせるなら、ワクチンは打たない方が感染拡大を防ぐことになるだろう。ちなみに、今の流行はコロナワクチンによる免疫破壊も関係しているのではないかと個人的には思っている。
マスコミは子どもが罹ると死亡する場合もあるといって恐怖を煽りワクチンに誘導するが、ワクチンはリスクよりベネフィットの方が大きい場合しか意味がない。いつまで「ワクチン神話」を流布しつづけるつもりだろうか。
百日ぜき道内で拡大 乳児は重症化の傾向 専門家「妊娠中のワクチン接種を」
昨今は感染症が流行ればすぐにワクチンを推奨する。新聞がこんな記事を出せば、ワクチンの追加接種をしようと思う人も増えるだろう。しかし、マスコミの推奨記事は、ワクチンの負の側面についてほとんど触れていない。
そこで、「ワクチン神話捏造の歴史」(ヒカルランド)から、百日咳ワクチンについて指摘されている問題点について箇条書きにして紹介しておきたい。
・19世紀に百日咳の死者はピークを迎え、百日咳ワクチンが使用される前にすでに99%以上死亡者が減少していた。
・現在の百日咳は以前より致死率が低下し、深刻な病気ではなくなった。
・百日咳ワクチンの接種により、急性脳症状や神経系の障害が生じることがあり、死亡することもある。
・ワクチンを接種した人は、5~10年後には百日咳に罹りやすくなる。
・乳児と幼児に投与される百日咳ワクチンは、3年後に有効性を失う。
・百日咳はワクチン接種率の高い集団において流行する病気。
・ワクチン接種者かどうかにかかわらず、保菌して伝播するのを防ぐ効果はないし、無症状感染者も多い。
・百日咳菌のワクチン耐性が生じている。
百日咳はワクチンを打つようになっても根絶されていない。子どもだけではなく大人も感染するし、無症状の場合も多い。ワクチンを打たずに自然感染した方が免疫は長持ちする一方で、接種者は抗原原罪により感染を拡大させるようだ。これらのリスクを考え合わせるなら、ワクチンは打たない方が感染拡大を防ぐことになるだろう。ちなみに、今の流行はコロナワクチンによる免疫破壊も関係しているのではないかと個人的には思っている。
マスコミは子どもが罹ると死亡する場合もあるといって恐怖を煽りワクチンに誘導するが、ワクチンはリスクよりベネフィットの方が大きい場合しか意味がない。いつまで「ワクチン神話」を流布しつづけるつもりだろうか。
2025年04月30日
ホシミミヨトウ
前翅の色彩や斑紋は変異が多いようだ。腎状紋は白く縁取られ、中にも白色部がある。幼虫はイネ科植物を食べるとのこと。写真の個体は前翅長14mm。ヤガ科キリガ亜科。

2022年8月5日 北海道十勝地方

2022年8月5日 北海道十勝地方
2025年04月29日
クサビヨトウ
前翅の地色は淡褐色で基部から前縁に沿って環状紋と腎状紋を囲むように暗色部がある。幼虫はイネ科植物を食べるとのこと。写真の個体は前翅長12mm。ヤガ科キリガ亜科。

2022年8月3日 北海道十勝地方
2022年8月3日 北海道十勝地方