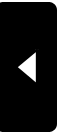鬼蜘蛛の網の片隅から › 自然・文化
2014年08月28日
土砂災害を軽減させるために
先日起きた広島での土石流災害では多数の方が亡くなり大惨事となった。その後、礼文島でも土砂崩れで住宅が押し流されお二人が亡くなった。昨年は伊豆大島で大規模な土砂災害があった。こうしたニュースを聞くたびに、未然に被害を防ぐことはできなかったのかと、やりきれない気持ちになる。
日本では毎年のように土石流被害が繰り返される。平地が限られ人口が多いために、どうしても山が迫っているようなところに住まざるを得ないという事情があるのはわかる。しかし、もっと被害を減らす工夫はできるのではなかろうか。
土砂災害にしても津波にしても自然の力は凄まじく、容赦なく襲いかかる。「備えあれば憂いなし」と言うが、いくら備えていても絶対に大丈夫とは言えない。まず災害が起きると想定されるところにはできる限り住まないのが望ましい。宅地を購入して家を建てるのであれば、災害の可能性も考えて場所を選ぶべきだろう。土砂崩れが起きないか、河川が溢れないか、断層はないか、液状化の恐れはないか、津波の心配はないか等々、頭に入れておくべきだ。住宅を借りるときも、災害に巻き込まれる危険性が少ない場所や建物を選ぶよう心がけた方がいい。
危険なところを宅地にしないよう規制すべきだと思うが、宅地造成をする業者はそんなことまで考慮しない。以下の記事を参照いただきたい。
判断の大切さ 住宅地造成をしてきた料理店主の話
本来なら危険な地域は居住禁止にするのが望ましいのだろうが、現実に多くの人が危険な場所に住んでおり、そのような人たちを速やかに安全な場所に移住させるのも不可能だ。とすれば、危険な地域に住んでいる人は、いざという時に避難できるようにしておくしかない。
集中豪雨を考えてみよう。土砂災害が起きるのは大雨が降り続くような時だ。しかし、バケツをひっくり返したような猛烈な雨が降っていたなら、普通、家から外に出ることすらためらってしまうだろう。避難勧告が出るまで待っていようという気持ちになるのも無理はない。
しかし、市町村などの避難勧告が当てにできないのはこれまでの事例からも明らかだ。避難勧告は必ず出されるわけではないし、避難勧告が出たときにはすでに時遅しということもある。だから、「この雨は尋常ではない」と感じたら、自主的に避難したり、少しでも安全な場所(鉄筋の建物とか、住宅なら二階など)に移動するしかない。大雨が降り続くときは、住民自身の適切な判断が生死を分けることになる。
避難の際も、車がある人は車で避難ということもできるが、徒歩で避難するにはかなりの覚悟がいる。傘だけではすぐにずぶぬれになるから、防水性のある雨具も用意したほうが賢明だ。また、どしゃぶりでは視界がきかず、夜などはさらに危険だ。高齢者や体の不自由な方は、ひとりでの避難はとても無理だろう。であれば、地域で連携するなどして日頃から弱者の対応を考えておくしかない。
すみやかに避難するためにも、自分の住んでいる場所の危険性を知っておくということはとても重要なことだ。
たいぶ前だが、郵便局に行ったら私の住んでいる地区のハザードマップが置いてあり、地滑りの危険個所が図示されていた。それまでは自分の住んでいる地域でそのような災害が起こりうるとは考えたこともなかったので、正直いってドッキリした。幸い私の住んでいるところは危険地域には入っていなかったが、危険地域には何件も家が建っている。果たしてそこに住んでいる人たちはその事実を知っているのだろうか?
実家の近くはどうなのかと、ネットでハザードマップを調べたこともある。丘陵を切り開いた住宅地だが、近くに危険区域に指定されている崖地があった。
日本各地を旅行しても、住宅の裏手が崖や急斜面になっているようなところはいくらでもあり、他人ごとでありながら「怖いなあ」と思ってしまう。山国の日本では、集中豪雨などで地滑りや土石流が起きそうな場所はいたるところにある。そして、昨今は土砂災害だけではなく、洪水や津波、火山など様々なハザードマップが作られるようになった。
災害を減らすには、まずは自分が住んでいるところが危険な場所であるかどうかをハザードマップできちんと認識することが大事だろう。そして、危険区域に住んでいるのであれば、大雨などの際にはすぐに避難できるように準備しておくことが肝要だと思う。
最後に一つ。地球温暖化の影響で異常気象が増えていると言われている。昨今の集中豪雨の増加も、その背景に人間活動が関わっている可能性がある。ならば、異常気象によって発生する自然災害は人類自身が引き起こしているわけで、単なる自然現象とは言い切れない。エネルギーの大量消費の見直しも真剣に取り組むべきではないか。
日本では毎年のように土石流被害が繰り返される。平地が限られ人口が多いために、どうしても山が迫っているようなところに住まざるを得ないという事情があるのはわかる。しかし、もっと被害を減らす工夫はできるのではなかろうか。
土砂災害にしても津波にしても自然の力は凄まじく、容赦なく襲いかかる。「備えあれば憂いなし」と言うが、いくら備えていても絶対に大丈夫とは言えない。まず災害が起きると想定されるところにはできる限り住まないのが望ましい。宅地を購入して家を建てるのであれば、災害の可能性も考えて場所を選ぶべきだろう。土砂崩れが起きないか、河川が溢れないか、断層はないか、液状化の恐れはないか、津波の心配はないか等々、頭に入れておくべきだ。住宅を借りるときも、災害に巻き込まれる危険性が少ない場所や建物を選ぶよう心がけた方がいい。
危険なところを宅地にしないよう規制すべきだと思うが、宅地造成をする業者はそんなことまで考慮しない。以下の記事を参照いただきたい。
判断の大切さ 住宅地造成をしてきた料理店主の話
本来なら危険な地域は居住禁止にするのが望ましいのだろうが、現実に多くの人が危険な場所に住んでおり、そのような人たちを速やかに安全な場所に移住させるのも不可能だ。とすれば、危険な地域に住んでいる人は、いざという時に避難できるようにしておくしかない。
集中豪雨を考えてみよう。土砂災害が起きるのは大雨が降り続くような時だ。しかし、バケツをひっくり返したような猛烈な雨が降っていたなら、普通、家から外に出ることすらためらってしまうだろう。避難勧告が出るまで待っていようという気持ちになるのも無理はない。
しかし、市町村などの避難勧告が当てにできないのはこれまでの事例からも明らかだ。避難勧告は必ず出されるわけではないし、避難勧告が出たときにはすでに時遅しということもある。だから、「この雨は尋常ではない」と感じたら、自主的に避難したり、少しでも安全な場所(鉄筋の建物とか、住宅なら二階など)に移動するしかない。大雨が降り続くときは、住民自身の適切な判断が生死を分けることになる。
避難の際も、車がある人は車で避難ということもできるが、徒歩で避難するにはかなりの覚悟がいる。傘だけではすぐにずぶぬれになるから、防水性のある雨具も用意したほうが賢明だ。また、どしゃぶりでは視界がきかず、夜などはさらに危険だ。高齢者や体の不自由な方は、ひとりでの避難はとても無理だろう。であれば、地域で連携するなどして日頃から弱者の対応を考えておくしかない。
すみやかに避難するためにも、自分の住んでいる場所の危険性を知っておくということはとても重要なことだ。
たいぶ前だが、郵便局に行ったら私の住んでいる地区のハザードマップが置いてあり、地滑りの危険個所が図示されていた。それまでは自分の住んでいる地域でそのような災害が起こりうるとは考えたこともなかったので、正直いってドッキリした。幸い私の住んでいるところは危険地域には入っていなかったが、危険地域には何件も家が建っている。果たしてそこに住んでいる人たちはその事実を知っているのだろうか?
実家の近くはどうなのかと、ネットでハザードマップを調べたこともある。丘陵を切り開いた住宅地だが、近くに危険区域に指定されている崖地があった。
日本各地を旅行しても、住宅の裏手が崖や急斜面になっているようなところはいくらでもあり、他人ごとでありながら「怖いなあ」と思ってしまう。山国の日本では、集中豪雨などで地滑りや土石流が起きそうな場所はいたるところにある。そして、昨今は土砂災害だけではなく、洪水や津波、火山など様々なハザードマップが作られるようになった。
災害を減らすには、まずは自分が住んでいるところが危険な場所であるかどうかをハザードマップできちんと認識することが大事だろう。そして、危険区域に住んでいるのであれば、大雨などの際にはすぐに避難できるように準備しておくことが肝要だと思う。
最後に一つ。地球温暖化の影響で異常気象が増えていると言われている。昨今の集中豪雨の増加も、その背景に人間活動が関わっている可能性がある。ならば、異常気象によって発生する自然災害は人類自身が引き起こしているわけで、単なる自然現象とは言い切れない。エネルギーの大量消費の見直しも真剣に取り組むべきではないか。
2013年06月16日
化粧品やトイレタリーの危険
私は基本的に化粧はしないし、化粧水すらほとんど使わない。理由はいろいろある。そもそも化粧そのものにほとんど興味がなく、化粧で見栄えを良くしたいと思わない。また化粧品の匂いが苦手で、特に自動車の中など狭い空間では香料の匂いで気持ちが悪くなる。化粧品をつけたときのベタベタした感触も好きになれない。しかし、何と言っても嫌なのは、得体の知れない化学物質を肌につけるという行為だ。
化粧品の成分にはさまざまな化学物質が含まれているが、そういうものを長時間肌につけるというのはどう考えても有害としか思えない。それに、化粧品を使わなくても肌にトラブルは生じない。だから、つける必要を感じないのだ。ごくたまに日差しの強い日に外出するとき日焼け止め入りのファンデーションをつけることがあるが、帰宅したらすぐに顔を洗う。気持ち悪くて仕方ないのだ。
同様に毛染めもしない。最近はかなり白髪が目立つようになってきたが、白髪染めをしたいとは思わない。第一に、髪や頭皮に良いわけがないから。それに、見かけだけ若くしたいとも思わない。白髪でも生き生きとして若々しい人は沢山いるし、何も髪の毛を染めてまで歳を隠す必要もないと思う。顔はどう見てもかなりの高齢なのに髪の毛は真黒という人をたまに見かけるが、かえって不自然だ。
女性が化粧をしたり白髪を染めるのは「マナー」「身だしなみ」などと言う人がいるが、いったい誰がそのようなことを決めたのだろう? 男性は化粧をしないのが当たり前なのに女性は化粧をするのが当然だという発想は、私にとっては性差別としか思えない。
化粧や染髪をしたい人がするのは自由だし、それを批判するつもりはないが、化粧しないことも個人の自由でありとやかく言われる筋合いではない。しかし、化粧品を長時間つけている女性は、化学物質のことを考えないのだろうかとは思う。それに、さまざまな科学物質が入った化粧品を洗い流すのは、水質汚濁や環境汚染にもつながるだろう。
オーストラリア発の話題とのことだが、以下のような指摘がある。
女性は化粧品・トイレタリーに含まれる化学物質を年間2キロ肌から吸収(世界の三面記事・オモロイド)
女性は年間平均2キロ、一日当たりにすると約5.5グラムもの化学物質を肌から吸収しているという。この数字は本当だろうか?と首をひねってしまうが、考えたら肌につける化粧品のほかに、それを落とすための化粧品にも化学物質が入っている。シャンプーやリンスなども入れたら、かなりの化学物質を肌から体内に取り込んでいることは確かだと思う。
私は髪の毛を洗うのも無添加石鹸を使っているから、シャンプーもリンスも使わない。石鹸での洗髪(リンスは酢を使用)に慣れてしまうと、市販のシャンプーはまったく使う気にならない。ボディーソープももちろん使わない。洗濯用洗剤も無添加の粉石鹸を使っている。無添加の固形石鹸と粉石鹸があれば何の不便もない。歯磨き剤も洗剤成分の入っていない「ノンフォーム」をたまに使うだけ。化粧品やトイレタリーから化学物質を吸収することはほとんどない生活をしている。
現代人は農薬をはじめとして様々な化学物質に汚染された食べ物を食べている。大気にも化学物質が漂っている。生活自体が化学物質にまみれているのだから健康を害するのは当然だ。アレルギーが増えている背景には、こうした汚染も関係しているのだろう。せめて生活必需品ではないトイレタリーなどは、極力減らしたほうがいい。メーカーの宣伝に乗せられるのは危険だと思う。
化粧品の成分にはさまざまな化学物質が含まれているが、そういうものを長時間肌につけるというのはどう考えても有害としか思えない。それに、化粧品を使わなくても肌にトラブルは生じない。だから、つける必要を感じないのだ。ごくたまに日差しの強い日に外出するとき日焼け止め入りのファンデーションをつけることがあるが、帰宅したらすぐに顔を洗う。気持ち悪くて仕方ないのだ。
同様に毛染めもしない。最近はかなり白髪が目立つようになってきたが、白髪染めをしたいとは思わない。第一に、髪や頭皮に良いわけがないから。それに、見かけだけ若くしたいとも思わない。白髪でも生き生きとして若々しい人は沢山いるし、何も髪の毛を染めてまで歳を隠す必要もないと思う。顔はどう見てもかなりの高齢なのに髪の毛は真黒という人をたまに見かけるが、かえって不自然だ。
女性が化粧をしたり白髪を染めるのは「マナー」「身だしなみ」などと言う人がいるが、いったい誰がそのようなことを決めたのだろう? 男性は化粧をしないのが当たり前なのに女性は化粧をするのが当然だという発想は、私にとっては性差別としか思えない。
化粧や染髪をしたい人がするのは自由だし、それを批判するつもりはないが、化粧しないことも個人の自由でありとやかく言われる筋合いではない。しかし、化粧品を長時間つけている女性は、化学物質のことを考えないのだろうかとは思う。それに、さまざまな科学物質が入った化粧品を洗い流すのは、水質汚濁や環境汚染にもつながるだろう。
オーストラリア発の話題とのことだが、以下のような指摘がある。
女性は化粧品・トイレタリーに含まれる化学物質を年間2キロ肌から吸収(世界の三面記事・オモロイド)
女性は年間平均2キロ、一日当たりにすると約5.5グラムもの化学物質を肌から吸収しているという。この数字は本当だろうか?と首をひねってしまうが、考えたら肌につける化粧品のほかに、それを落とすための化粧品にも化学物質が入っている。シャンプーやリンスなども入れたら、かなりの化学物質を肌から体内に取り込んでいることは確かだと思う。
私は髪の毛を洗うのも無添加石鹸を使っているから、シャンプーもリンスも使わない。石鹸での洗髪(リンスは酢を使用)に慣れてしまうと、市販のシャンプーはまったく使う気にならない。ボディーソープももちろん使わない。洗濯用洗剤も無添加の粉石鹸を使っている。無添加の固形石鹸と粉石鹸があれば何の不便もない。歯磨き剤も洗剤成分の入っていない「ノンフォーム」をたまに使うだけ。化粧品やトイレタリーから化学物質を吸収することはほとんどない生活をしている。
現代人は農薬をはじめとして様々な化学物質に汚染された食べ物を食べている。大気にも化学物質が漂っている。生活自体が化学物質にまみれているのだから健康を害するのは当然だ。アレルギーが増えている背景には、こうした汚染も関係しているのだろう。せめて生活必需品ではないトイレタリーなどは、極力減らしたほうがいい。メーカーの宣伝に乗せられるのは危険だと思う。
2013年03月03日
土木工事による防災より避難対策を重視すべき
私はこれまで調査や旅行で道内各地にでかけているが、いつも思うのが津波や火山に対する考えが甘い人が多いのではないかということだ。
たとえば、大津波がきたらひとたまりもない海岸に家を建てて生活している人が非常に多い。多くは漁業を生業としている人たちだ。そんなところを通るたびに、「よくこんな危険なところに住んでいるなあ・・・」と他人事ながら思ってしまう。裏手に高台や山があり容易に避難できるようなところはまだしも、背後が絶壁で簡単に避難できないようなところ、あるいは平地が広がっていて近くに高台がないところにも人々は住みついている。
そもそも、裏手に高台があるのなら高台のほうに家を建て、海岸は番屋だけにしておけばいいのに、と思うのだが、やはり利便性を優先してしまうのだろう。それに、人というのは「自分の生きている間には大津波は来ないだろう」と高をくくってしまうのかもしれない。地震大国に住んでいる以上、大津波がくる可能性を知らないわけがない。知っていながらも利便性の方を選んでそこに住んでいるのだ。
火山の噴火もそうだ。洞爺湖はそれなりの規模の温泉街が広がっているが、有珠山はいつ噴火してもおかしくない。有珠山の場合、噴火に備えて観測をしており、噴火の兆候が現れたらすぐに避難する体制ができてはいるが、私にしてみればなぜそんな危険なところに住みつくのかと不思議でならない。
十勝岳の山腹にある白金温泉や十勝岳温泉も同じだ。ここでは噴火による被害を軽減させることを目的に砂防施設を整備している。たとえば、噴火に伴って発生する泥流による被害を軽減させるための砂防堰堤が美瑛川や富良野川に造られている。また、白金地区では十勝岳火山砂防情報センターという立派な施設が建設され、噴火の際の住民の避難場所にもなっている。
しかし、泥流を流下させるための施設を造ったからといって決して安全が確保されているわけではない。大規模な泥流や火砕流が発生したなら、この程度の施設は焼け石に水だろう。住民は建造物をあきらめて避難するしかない。大規模噴火があったなら被害にあうのを承知で住んでいるということなのだろう。
限られた住民しかいないところで、防災のための土木工事に巨額の費用をかけるべきなのだろうかと、いつも思う。
3.11の大津波で、国は防災強化のための土木工事を加速させようとしている。堤防のかさ上げや強化、防波堤の建設などだ。しかし、なんでも土木工事で対処しようとすべきではないだろう。高台に避難できるようなところでは避難を優先すべきだし、そもそも避難するような場所がないところは、できる限り居住地にするのを避け農地などとして利用したほうがいい。少なくとも将来的にはそうしていくべきだと思う。
3.11では函館も標高の低いところでは浸水した。釧路のようにかなりの人が住んでいて高台も近くにないところでは津波対策は必要だ。釧路市の津波のハザードマップを見たら、根室沖から十勝沖を震源とするマグニチュード8.5の地震が起き、津波の最大水位が4~13メートル(釧路港で約5メートル)、津波到達時間30~40分の場合のマップが公開されているが、もっと規模の大きな地震も想定しておく必要があるだろう。
釧路市の津波ハザードマップ
仮に20メートルの津波がきたら、釧路の市街地は全域が水没する。以下のサイトから浸水域の想定を見ることができる。
津波浸水マップ
しかし、津波を土木工事で止めようとしても限界がある。3.11の大津波で、1200億円もかけて造られた釜石の防波堤はあっけなく壊れてしまった。所詮、人が構造物で自然災害を防ごうとしても限界がある。防波堤に巨額の税金を投じるより、徒歩で避難できる範囲に点々と避難場所となる免震建造物を建てたほうがいいのではなかろうか。
3.11以降、大地震や大津波、火山の噴火が懸念されている。地震も火山もプレートの動きと密接な関係にあるからだ。日本ではいつ大地震や大津波が起きるか分からないし、これから火山活動も活発になるだろう。箱根でも地震活動が活発化しているし、富士山も近い将来噴火する可能性が高い。しかし人々はあまりに無防備に麓に住みついてしまった。災害は忘れたころにやってくるのである。
箱根で不気味な地震が頻発 専門家は「最大の警戒が必要」
3年で富士山は噴火する そのときに備えたほうがいい(現代ビジネス)
大都市や近代文明は災害に弱く、火山噴火や津波などの自然災害そのものには何の手も打てない。津波被害や火山による被害が想定されるところに住んでいる人たちは、いざという時のために防災や避難について常に頭に描き準備しておいたほうがよさそうだ。
たとえば、大津波がきたらひとたまりもない海岸に家を建てて生活している人が非常に多い。多くは漁業を生業としている人たちだ。そんなところを通るたびに、「よくこんな危険なところに住んでいるなあ・・・」と他人事ながら思ってしまう。裏手に高台や山があり容易に避難できるようなところはまだしも、背後が絶壁で簡単に避難できないようなところ、あるいは平地が広がっていて近くに高台がないところにも人々は住みついている。
そもそも、裏手に高台があるのなら高台のほうに家を建て、海岸は番屋だけにしておけばいいのに、と思うのだが、やはり利便性を優先してしまうのだろう。それに、人というのは「自分の生きている間には大津波は来ないだろう」と高をくくってしまうのかもしれない。地震大国に住んでいる以上、大津波がくる可能性を知らないわけがない。知っていながらも利便性の方を選んでそこに住んでいるのだ。
火山の噴火もそうだ。洞爺湖はそれなりの規模の温泉街が広がっているが、有珠山はいつ噴火してもおかしくない。有珠山の場合、噴火に備えて観測をしており、噴火の兆候が現れたらすぐに避難する体制ができてはいるが、私にしてみればなぜそんな危険なところに住みつくのかと不思議でならない。
十勝岳の山腹にある白金温泉や十勝岳温泉も同じだ。ここでは噴火による被害を軽減させることを目的に砂防施設を整備している。たとえば、噴火に伴って発生する泥流による被害を軽減させるための砂防堰堤が美瑛川や富良野川に造られている。また、白金地区では十勝岳火山砂防情報センターという立派な施設が建設され、噴火の際の住民の避難場所にもなっている。
しかし、泥流を流下させるための施設を造ったからといって決して安全が確保されているわけではない。大規模な泥流や火砕流が発生したなら、この程度の施設は焼け石に水だろう。住民は建造物をあきらめて避難するしかない。大規模噴火があったなら被害にあうのを承知で住んでいるということなのだろう。
限られた住民しかいないところで、防災のための土木工事に巨額の費用をかけるべきなのだろうかと、いつも思う。
3.11の大津波で、国は防災強化のための土木工事を加速させようとしている。堤防のかさ上げや強化、防波堤の建設などだ。しかし、なんでも土木工事で対処しようとすべきではないだろう。高台に避難できるようなところでは避難を優先すべきだし、そもそも避難するような場所がないところは、できる限り居住地にするのを避け農地などとして利用したほうがいい。少なくとも将来的にはそうしていくべきだと思う。
3.11では函館も標高の低いところでは浸水した。釧路のようにかなりの人が住んでいて高台も近くにないところでは津波対策は必要だ。釧路市の津波のハザードマップを見たら、根室沖から十勝沖を震源とするマグニチュード8.5の地震が起き、津波の最大水位が4~13メートル(釧路港で約5メートル)、津波到達時間30~40分の場合のマップが公開されているが、もっと規模の大きな地震も想定しておく必要があるだろう。
釧路市の津波ハザードマップ
仮に20メートルの津波がきたら、釧路の市街地は全域が水没する。以下のサイトから浸水域の想定を見ることができる。
津波浸水マップ
しかし、津波を土木工事で止めようとしても限界がある。3.11の大津波で、1200億円もかけて造られた釜石の防波堤はあっけなく壊れてしまった。所詮、人が構造物で自然災害を防ごうとしても限界がある。防波堤に巨額の税金を投じるより、徒歩で避難できる範囲に点々と避難場所となる免震建造物を建てたほうがいいのではなかろうか。
3.11以降、大地震や大津波、火山の噴火が懸念されている。地震も火山もプレートの動きと密接な関係にあるからだ。日本ではいつ大地震や大津波が起きるか分からないし、これから火山活動も活発になるだろう。箱根でも地震活動が活発化しているし、富士山も近い将来噴火する可能性が高い。しかし人々はあまりに無防備に麓に住みついてしまった。災害は忘れたころにやってくるのである。
箱根で不気味な地震が頻発 専門家は「最大の警戒が必要」
3年で富士山は噴火する そのときに備えたほうがいい(現代ビジネス)
大都市や近代文明は災害に弱く、火山噴火や津波などの自然災害そのものには何の手も打てない。津波被害や火山による被害が想定されるところに住んでいる人たちは、いざという時のために防災や避難について常に頭に描き準備しておいたほうがよさそうだ。
2013年02月06日
異議申し立てや議論を嫌う人たち
先日、ある集まりで、若い人たちが自然保護団体に入ってこないということが話題になった。これは私が関わっている自然保護団体だけの問題ではない。恐らく全国的な傾向だろう。
私が学生の頃は、自然保護団体は若い人たちが多く活気があった。全国自然保護連合の大会なども若い人たちから年配の人たちまで集って熱い議論が展開された。ところが、今は多くの自然保護団体で高齢化が進んでいる。かつて自然保護団体で頑張っていた若い人たちが、今でもそのまま活動を担っているのだ。だから自然保護団体の中心メンバーは今では50代から70代になっていて、平均年齢が毎年1歳ずつ上がっているといっても過言ではない。若い人たちがほとんど育っていない。
若い人たちは携帯電話やスマートフォンの普及で金銭的にも時間的にも余裕がなくなっているということもあるだろう。しかし、若者が自然保護運動に参加しなくなったのはかなり前からのことで、若者の貧困化とは直接関係がなさそうだ。
では、若い人たちは物事に積極的に取り組むことをしなくなったのか? そんなことはない。たとえば札幌で毎年行われている「よさこいソーラン祭り」は若い人たちが始めたイベントで、参加者は圧倒的に若い人が多い。しかもすごいエネルギーだ。災害復興のボランティアに行く若者もそれなりにいる。ほかにもボランティア活動に参加する若者はある程度いると思う。若者からエネルギーがなくなったわけではないし、社会的活動に無関心というわけでもない。また自然に関心がある若者がいなくなったわけでもない。ところが自然保護団体は若者から敬遠される。なぜなのか?
自然保護活動というのは開発行為の事業主体である行政機関や企業との交渉、話し合い、要請行動などが必須だ。つまり、理論でぶつかり合うことが避けられないし、それが運動の中心とならざるを得ない。仲良しクラブ的な感覚ではできない。しかし、今の若者はそのようなことに関わることを好まない。「よさこいソーラン祭り」もボランティア活動も、そこには「ぶつかり合い」「行政などとの対峙」がない。今の若者は「異議申し立て」することを敬遠しているとしか思えない。
若者を見ていれば、それは自ずと納得がいく。つまり、若者たちは「周りの人の話しに合わせて浮かないようにする」「空気を読んで、その場を乱すようなことは言わない」「声の大きい人に合わせてふるまう」ということを徹底的に身につけているのだ。そうしなければいじめにあう。だから、たとえ心の中で「おかしい」と思うことがあっても、口には出さない。また自分が他者からどのように評価されるかをとても気にしている人が多い。だから意見を言うのが苦手だし、本音を隠すこともある。子どものころから、そうした感覚がしみついている。理不尽なことがあっても、なかなか「異議申し立てをする」という行動をとらず、ストレスを抱えて引きこもってしまうこともある。
このような感覚の人たちは「異議申し立て」をすることがメインの自然保護活動は、とても馴染めないに違いない。もちろんこういった活動は楽しくもないし、理詰めの議論を要求される。
ある教員退職者は、若者が異議申し立てをしなくなっているのは教育の影響だという。教育現場においても、異議申し立てをするような姿勢を避ける教育がなされてきたという。ここ数十年でその傾向が非常に強くなっているそうだ。
もっとも、こうしたことを敬遠するのは、若い人に限ったことではない。異議申し立てをしない、議論を避けるという行動パターンは、私と同世代の人たちにも広く浸透してきている。波風を立てることを嫌うのだ。だからこそ、子どもたちにもそういう影響が色濃く出る。近年、それは一段と強まっているように思う。
仲間内のメーリングなどでの議論を嫌う人も多い。たとえば自分たちのグループの運営問題ですら、議論による意思決定を敬遠する傾向がある。意見を求められても沈黙して意思表示を避けてしまう人も多い。運営について意見を述べたり議論することが「活動の足を引っ張る」「建設的ではない」と捉え、批判する人もいる。その結果、声の大きな人に従うようになってしまい対等な関係が損なわれる。議論を避けてしまえば、民主的な組織運営から遠ざかってしまう。どこかおかしくはないか。
おそらく、ここ数十年のあいだに、教育現場も含め社会全体にそういう意識が蔓延してきているのではなかろうか。論理的に物事を考えることをやめ、体制に従ってしまうという空気が日本全体に漂っている。学校でも「考える力」を身につける教育はせず、テストの点数に重点が置かれた教育しかしない。これでは批判的な思考力が育つわけがない。国民を意のままに操りたい政府にとって「おとなしい国民」は思う壺に違いない。議論や異議申し立てをしない人たちは、権力者に支配されるしかない。
原発事故で多くの人が安全神話に騙されていたことに目が覚めた。原子力ムラの嘘と隠蔽に大半の国民が怒り、全国で脱原発デモ、集会、電力会社への抗議行動などを繰り広げた。脱原発を求める人たちが代々木公園を埋め尽くした光景は、今までなら考えられないことだった。原発事故を契機に「異議申し立て」をする国民へと意識が変わりつつあるのだろうか?
たしかに、あの事故で目覚めた人はそれなりにいるだろう。しかし、私には大半の人が根本的な意識変革には至っていないと思えてならない。もう原発事故のことなど忘れてしまったような人があまりに多いように見えて仕方ないからだ。
アメリカ人にとって、はっきりと意思表示をしない日本人と話しても面白くない、という話しを聞いたことがある。日本人は逆で、協調性を重視し、議論をふっかけたり異議を唱える人を敬遠する。「議論」や「異議申し立て」をもっと前向きに捉えていく必要があるのではなかろうか。
私が学生の頃は、自然保護団体は若い人たちが多く活気があった。全国自然保護連合の大会なども若い人たちから年配の人たちまで集って熱い議論が展開された。ところが、今は多くの自然保護団体で高齢化が進んでいる。かつて自然保護団体で頑張っていた若い人たちが、今でもそのまま活動を担っているのだ。だから自然保護団体の中心メンバーは今では50代から70代になっていて、平均年齢が毎年1歳ずつ上がっているといっても過言ではない。若い人たちがほとんど育っていない。
若い人たちは携帯電話やスマートフォンの普及で金銭的にも時間的にも余裕がなくなっているということもあるだろう。しかし、若者が自然保護運動に参加しなくなったのはかなり前からのことで、若者の貧困化とは直接関係がなさそうだ。
では、若い人たちは物事に積極的に取り組むことをしなくなったのか? そんなことはない。たとえば札幌で毎年行われている「よさこいソーラン祭り」は若い人たちが始めたイベントで、参加者は圧倒的に若い人が多い。しかもすごいエネルギーだ。災害復興のボランティアに行く若者もそれなりにいる。ほかにもボランティア活動に参加する若者はある程度いると思う。若者からエネルギーがなくなったわけではないし、社会的活動に無関心というわけでもない。また自然に関心がある若者がいなくなったわけでもない。ところが自然保護団体は若者から敬遠される。なぜなのか?
自然保護活動というのは開発行為の事業主体である行政機関や企業との交渉、話し合い、要請行動などが必須だ。つまり、理論でぶつかり合うことが避けられないし、それが運動の中心とならざるを得ない。仲良しクラブ的な感覚ではできない。しかし、今の若者はそのようなことに関わることを好まない。「よさこいソーラン祭り」もボランティア活動も、そこには「ぶつかり合い」「行政などとの対峙」がない。今の若者は「異議申し立て」することを敬遠しているとしか思えない。
若者を見ていれば、それは自ずと納得がいく。つまり、若者たちは「周りの人の話しに合わせて浮かないようにする」「空気を読んで、その場を乱すようなことは言わない」「声の大きい人に合わせてふるまう」ということを徹底的に身につけているのだ。そうしなければいじめにあう。だから、たとえ心の中で「おかしい」と思うことがあっても、口には出さない。また自分が他者からどのように評価されるかをとても気にしている人が多い。だから意見を言うのが苦手だし、本音を隠すこともある。子どものころから、そうした感覚がしみついている。理不尽なことがあっても、なかなか「異議申し立てをする」という行動をとらず、ストレスを抱えて引きこもってしまうこともある。
このような感覚の人たちは「異議申し立て」をすることがメインの自然保護活動は、とても馴染めないに違いない。もちろんこういった活動は楽しくもないし、理詰めの議論を要求される。
ある教員退職者は、若者が異議申し立てをしなくなっているのは教育の影響だという。教育現場においても、異議申し立てをするような姿勢を避ける教育がなされてきたという。ここ数十年でその傾向が非常に強くなっているそうだ。
もっとも、こうしたことを敬遠するのは、若い人に限ったことではない。異議申し立てをしない、議論を避けるという行動パターンは、私と同世代の人たちにも広く浸透してきている。波風を立てることを嫌うのだ。だからこそ、子どもたちにもそういう影響が色濃く出る。近年、それは一段と強まっているように思う。
仲間内のメーリングなどでの議論を嫌う人も多い。たとえば自分たちのグループの運営問題ですら、議論による意思決定を敬遠する傾向がある。意見を求められても沈黙して意思表示を避けてしまう人も多い。運営について意見を述べたり議論することが「活動の足を引っ張る」「建設的ではない」と捉え、批判する人もいる。その結果、声の大きな人に従うようになってしまい対等な関係が損なわれる。議論を避けてしまえば、民主的な組織運営から遠ざかってしまう。どこかおかしくはないか。
おそらく、ここ数十年のあいだに、教育現場も含め社会全体にそういう意識が蔓延してきているのではなかろうか。論理的に物事を考えることをやめ、体制に従ってしまうという空気が日本全体に漂っている。学校でも「考える力」を身につける教育はせず、テストの点数に重点が置かれた教育しかしない。これでは批判的な思考力が育つわけがない。国民を意のままに操りたい政府にとって「おとなしい国民」は思う壺に違いない。議論や異議申し立てをしない人たちは、権力者に支配されるしかない。
原発事故で多くの人が安全神話に騙されていたことに目が覚めた。原子力ムラの嘘と隠蔽に大半の国民が怒り、全国で脱原発デモ、集会、電力会社への抗議行動などを繰り広げた。脱原発を求める人たちが代々木公園を埋め尽くした光景は、今までなら考えられないことだった。原発事故を契機に「異議申し立て」をする国民へと意識が変わりつつあるのだろうか?
たしかに、あの事故で目覚めた人はそれなりにいるだろう。しかし、私には大半の人が根本的な意識変革には至っていないと思えてならない。もう原発事故のことなど忘れてしまったような人があまりに多いように見えて仕方ないからだ。
アメリカ人にとって、はっきりと意思表示をしない日本人と話しても面白くない、という話しを聞いたことがある。日本人は逆で、協調性を重視し、議論をふっかけたり異議を唱える人を敬遠する。「議論」や「異議申し立て」をもっと前向きに捉えていく必要があるのではなかろうか。
2013年01月07日
消えゆく心の豊かさ
沖縄在住の「木枯」さんのブログの今年はじめの記事に、木枯さんがインドを旅したときの写真が掲載されている。実に生き生きと輝いた目をしているインドの子どもたちの写真に、私はしばし見入ってしまった。
いちごいちえ
そして、すぐに故渡辺容子さんがフィリピンに行ったときの写真を思い出した。そこには木枯さんの写真と同じような子どもたちの笑顔があった。
1994年フィリピンの子どもたち
彼女はその前の年にネパールにも行って子どもたちの写真を撮っている。
1993年ネパールの子どもたち
インドの子どもたちも、フィリピンの子どもたちも、ネパールの子どもたちもとても生き生きとした顔をしている。ちょっとはにかみながらも、屈託のない笑顔、豊かな表情。今の日本の子どもたちに、こんな笑顔を見つけることができるだろうか?
彼女がフィリピンの子どもたちについて書いた文章がある。
フィリピンにて
できれば全文を読んでもらいたいのだが、最後の部分をここに引用したい。
写真からも分かるように、彼らの生活は物質的にはひどく貧しい。それゆえに、子どもとて家の仕事を手伝うのが当たり前の生活。たぶん文句を言うこともなく、当たり前の日常として仕事をこなしているに違いない。もちろん、今は渡辺さんがこの文を書いたときとは状況が変わっているのだろうが、こんな生活をしている人たちは世界にはまだまだ沢山いる。溢れる物に囲まれている今の日本の子どもたちには想像もつかない世界だろう。
私が子ども時代を過ごした頃はまだ物も少なくて、少なくとも精神的には今よりもはるかに健全だったのだと思う。ちょうど、「ALWAYS三丁目の夕日」のあの時代、あの風景だ。今はいたるところに物が溢れて生活も便利になった。鉛筆1本も大事に使った子どもの頃の生活が嘘のようだ。その反面、「人間の最も基本的で人間らしい生活」がどんどん無くなっている。子どもも大人も、周りの人の顔色を窺いながら本音を隠し、自分を殺して生きている。そこから屈託のない笑顔など生まれるはずもない。それで本当に私たちは幸せになったのだろうか?
もちろん、昭和時代のような生活に戻るべきだというつもりはないし、そんなことにはならないだろう。しかし、社会のありようがあまりに非人間的になっていることに改めて驚かされる。私たち人類はいったいどこまで物質的豊かさや利便性を追求しつづけるのだろうか? それが本当に豊かな生活なのだろうか?
渡辺さんも書いているように、不安を見ないようにしているうちに、私たちは管理され操られていた。そしてとんでもない格差社会になり、原発も爆発してしまった。彼女がいっていた通り「とりかえしのつかないこと」になってきている。
生き生きとした子どもたちの写真は、人間にとって本当に大切なものを思い出させてくれる。
さだまさし氏の「やはり僕たちの国は残念だけど何か大切な処で道を間違えたようですね」という言葉を、どれほどの日本人が実感しているのだろうか。
いちごいちえ
そして、すぐに故渡辺容子さんがフィリピンに行ったときの写真を思い出した。そこには木枯さんの写真と同じような子どもたちの笑顔があった。
1994年フィリピンの子どもたち
彼女はその前の年にネパールにも行って子どもたちの写真を撮っている。
1993年ネパールの子どもたち
インドの子どもたちも、フィリピンの子どもたちも、ネパールの子どもたちもとても生き生きとした顔をしている。ちょっとはにかみながらも、屈託のない笑顔、豊かな表情。今の日本の子どもたちに、こんな笑顔を見つけることができるだろうか?
彼女がフィリピンの子どもたちについて書いた文章がある。
フィリピンにて
できれば全文を読んでもらいたいのだが、最後の部分をここに引用したい。
それにしても、カバジャガンの人たちの笑顔は豊かで美しかった。大人も子どもも、美しい海と空とゆったりと流れる時間の中で、「食べて住んで、そして楽しむ」という、人間の最も基本的で人間らしい生活を、日々自分自身の手で紡いでいた。美しい豊かな笑顔は、その喜びに裏打ちされているのだった。
ふりかえって、今の日本に住む私たちはどうだろう。そんな自然な暮らしとはほど遠いところへ来てしまった。今となっては、戻ることなどできはしない。それはわかっているけれど・・・。カバジャガンにはまだあるような、真の意味での豊かさが失われ、物ばかりあふれ、時間に追われ、効率だけが求められ、友だちと1本のギターを共有するのではなく、友だちをけおとし、自分が出世しなければならない日本の生活、そういう日常生活それ自体が、今、子どもたちに襲いかかって、押しつぶそうとしているのではないだろうか。それはもちろん、子どもばかりでなく、大人も同じである。
今の時代の<不安>の中で、大人もまた自分の心を偽っている。こんなふうに物があふれ、次から次へとコマーシャルなどの刺激によって欲望を生み出さされ、物(文化も含め)を消費することだけを押しつけられているような、すべてが管理、操作されている世の中。そこでは、自分のやっていることをちょっと立ち止まって考えてみることすら、相当意識的にやらないと、できないで流されていく一方だと思う。流されているうちに、自分が本当に大切にしたいものなど、ひとつ残らず忘れてしまった。
最後に残された人間らしさが、<不安>だけを感じている。その<不安>が見えてしまったらこわいから、自己防衛本能でみんなそっちを見ないようにしている。だから、むしろ望んで管理、操作されているのではないか。こうなると悪循環だ。管理、操作され、自分を見失う。すると<不安>になるから、自分を見たくなくて、管理、操作されたがる。
でも、そうやって逃げてばかりいると、いまにきっととりかえしのつかないことになる。それに、<不安>は確実にあるのだから、永遠に逃げ回っているわけにはいかない。勇気をもって立ち止まるしかない。そして、ふりかえって、<不安>をしっかりと見据え、対決するのだ。
写真からも分かるように、彼らの生活は物質的にはひどく貧しい。それゆえに、子どもとて家の仕事を手伝うのが当たり前の生活。たぶん文句を言うこともなく、当たり前の日常として仕事をこなしているに違いない。もちろん、今は渡辺さんがこの文を書いたときとは状況が変わっているのだろうが、こんな生活をしている人たちは世界にはまだまだ沢山いる。溢れる物に囲まれている今の日本の子どもたちには想像もつかない世界だろう。
私が子ども時代を過ごした頃はまだ物も少なくて、少なくとも精神的には今よりもはるかに健全だったのだと思う。ちょうど、「ALWAYS三丁目の夕日」のあの時代、あの風景だ。今はいたるところに物が溢れて生活も便利になった。鉛筆1本も大事に使った子どもの頃の生活が嘘のようだ。その反面、「人間の最も基本的で人間らしい生活」がどんどん無くなっている。子どもも大人も、周りの人の顔色を窺いながら本音を隠し、自分を殺して生きている。そこから屈託のない笑顔など生まれるはずもない。それで本当に私たちは幸せになったのだろうか?
もちろん、昭和時代のような生活に戻るべきだというつもりはないし、そんなことにはならないだろう。しかし、社会のありようがあまりに非人間的になっていることに改めて驚かされる。私たち人類はいったいどこまで物質的豊かさや利便性を追求しつづけるのだろうか? それが本当に豊かな生活なのだろうか?
渡辺さんも書いているように、不安を見ないようにしているうちに、私たちは管理され操られていた。そしてとんでもない格差社会になり、原発も爆発してしまった。彼女がいっていた通り「とりかえしのつかないこと」になってきている。
生き生きとした子どもたちの写真は、人間にとって本当に大切なものを思い出させてくれる。
さだまさし氏の「やはり僕たちの国は残念だけど何か大切な処で道を間違えたようですね」という言葉を、どれほどの日本人が実感しているのだろうか。
タグ :豊かさ
2012年10月01日
家庭菜園から利便性追及社会の矛盾を考える
今年の北海道は9月中旬まで暑いくらいの気候だったこともあり、家庭菜園のハーブの収穫ものんびりとしていたのだが、下旬になって一気に寒くなってきた。とはいっても平年並みなのだが。
考えてみれば、9月も下旬になればいつ霜が降りてもおかしくない。10月中旬には紅葉の最盛期を迎える。植物ももうじき生長を停止する季節だ。そう思って、あわててペパーミント、レモンバーム、スイートバジル、パセリなどの収穫を始めた。これらは乾燥させてハーブティーや料理に使う。
下の写真は収穫したスイートバジルとパセリ。収穫してから水洗いをし、ザルに入れて水を切ったところ。

これをネットに入れて乾燥させる。左のカゴの一番上の段がパセリで、真中と下の段がスイートバジル。右のカゴは3段ともペパーミント。

そのあとはバットに広げて窓辺に置き、仕上げの乾燥をする(そのままカゴで乾燥させてもいいのだが、次々と収穫するのでこのようにしている)。写真はレモンバーム。なんだかナキウサギの貯食みたいだ(ナキウサギは秋になると雨の当たらない岩の下などに植物を運んで乾燥させ、冬の間の食料にする)。

カラカラに乾燥したら、手で揉んで茎から葉を落とし、チャック付きポリ袋や瓶などに入れて保存する。
下は収穫したカレンデュラ(金盞花)。寒さには強いので、霜が降りるまで花をつけそうだ。花弁をむしって、バットや缶に広げて日当たりのいい窓辺で乾かす。天気がよいとオレンジ色が鮮やかなまま乾燥できるが、天気が悪くて乾燥に時間がかかると黒ずんでしまう。カレンデュラは肌に良いそうで、ハーブティーのほか化粧水などを作るのにも使う。


家庭菜園をやっていてつくづく思うのは、作物をつくるという経験は生物である人にとってとても意義深いものであるということだ。生きるうえで必須の食物をつくるという作業は、自然から糧を得ることであるし、環境問題とも切り離せない。さまざまなことを考えさせられる。
今年はウリハムシモドキが大発生し、レモンバームやスイートバジル、ペパーミントの葉が次々と穴だらけになっていった。はじめのうちは静観していたのだが、このまま放置したら収穫も危ぶまれる状況だと判断し、途中から手作業で防除をはじめた。その甲斐があってか、収穫前には元気を取り戻した。虫の発生や病気への対処は農薬などの問題を考えることにつながる。
そもそも同じ種類の作物を大面積でつくれば、それを好む虫が大発生するのは自然の理にかなっている。それを農薬で押さえ込もうとすれば、やがてどこかにしわ寄せがくる。環境汚染であり生物濃縮だ。やがて虫は農薬に耐性を持つようになり、悪循環に陥ってしまう。作物をつくるということはこういう自然の摂理を知ることだし、手間暇を惜しんではならないことを身をもって体験できる。家庭菜園であれば、いろいろな作物をモザイク状に植えたほうがいいのだろう。除草もほどほどが良いのかもしれない。
北海道の農業は機械と農薬によって大規模化が進んでいる。しかし、そのしわ寄せがあとからくるのだ。農業に限らず、何でも利便性を追求していたら、やがてそのしわ寄せがドッと押し寄せてくるのだろう。人が生物であり生態系の一員である以上、大規模化や利便性追及はほどほどにしなければならないと思う。
実際に、農薬・機械まかせの大規模農家が大多数を占める一方で、無農薬有機栽培で頑張っている小規模農家も少数ながらある。どちらが自然と共存した健全なスタイルなのかは言うまでもない。
一極集中を目指して大都市ばかり人口が増え続け、地方は過疎化が進むという構造も同じではなかろうか。大地震などの大災害に襲われれば、大都市はひとたまりもないだろう。大きな被害を出すうえに復興にはとんでもない時間と費用がかかる。地方で大地震が起きても被害が少ないのは歴然とした事実だ。東京にあれほどの高層ビル群を建ててしまったことは間違いだったと思わざるを得ない。方針転換をして地方を大事にすべきだと思う。
北海道では、都市近郊の大型店の増加も地方の小売店を潰してきた。住んでいる地域で買い物ができなければ、高齢者などの弱者を切り捨てることになる。大企業、大型店ばかり優遇すれば、そのツケが必ず弱者に回ってくる。そして過疎化が進めば、医療も福祉も切り捨てられる。
発電にしても、大形の発電所に頼るのではなく、できる限りそれぞれの地域で賄うシステムにしていくべきではないか。メガソーラーも疑問だ。地方に人を分散させ、電気もできる限り地域で自給自足できるようにする政策こそ必要なのではなかろうか。
人間の欲望は尽きない。しかし、そろそろこの矛盾に気づいて方向転換しないと、取り返しのつかないことになるだろう。もう、その分岐点を過ぎてしまったかもしれないが・・・。
考えてみれば、9月も下旬になればいつ霜が降りてもおかしくない。10月中旬には紅葉の最盛期を迎える。植物ももうじき生長を停止する季節だ。そう思って、あわててペパーミント、レモンバーム、スイートバジル、パセリなどの収穫を始めた。これらは乾燥させてハーブティーや料理に使う。
下の写真は収穫したスイートバジルとパセリ。収穫してから水洗いをし、ザルに入れて水を切ったところ。

これをネットに入れて乾燥させる。左のカゴの一番上の段がパセリで、真中と下の段がスイートバジル。右のカゴは3段ともペパーミント。

そのあとはバットに広げて窓辺に置き、仕上げの乾燥をする(そのままカゴで乾燥させてもいいのだが、次々と収穫するのでこのようにしている)。写真はレモンバーム。なんだかナキウサギの貯食みたいだ(ナキウサギは秋になると雨の当たらない岩の下などに植物を運んで乾燥させ、冬の間の食料にする)。

カラカラに乾燥したら、手で揉んで茎から葉を落とし、チャック付きポリ袋や瓶などに入れて保存する。
下は収穫したカレンデュラ(金盞花)。寒さには強いので、霜が降りるまで花をつけそうだ。花弁をむしって、バットや缶に広げて日当たりのいい窓辺で乾かす。天気がよいとオレンジ色が鮮やかなまま乾燥できるが、天気が悪くて乾燥に時間がかかると黒ずんでしまう。カレンデュラは肌に良いそうで、ハーブティーのほか化粧水などを作るのにも使う。


家庭菜園をやっていてつくづく思うのは、作物をつくるという経験は生物である人にとってとても意義深いものであるということだ。生きるうえで必須の食物をつくるという作業は、自然から糧を得ることであるし、環境問題とも切り離せない。さまざまなことを考えさせられる。
今年はウリハムシモドキが大発生し、レモンバームやスイートバジル、ペパーミントの葉が次々と穴だらけになっていった。はじめのうちは静観していたのだが、このまま放置したら収穫も危ぶまれる状況だと判断し、途中から手作業で防除をはじめた。その甲斐があってか、収穫前には元気を取り戻した。虫の発生や病気への対処は農薬などの問題を考えることにつながる。
そもそも同じ種類の作物を大面積でつくれば、それを好む虫が大発生するのは自然の理にかなっている。それを農薬で押さえ込もうとすれば、やがてどこかにしわ寄せがくる。環境汚染であり生物濃縮だ。やがて虫は農薬に耐性を持つようになり、悪循環に陥ってしまう。作物をつくるということはこういう自然の摂理を知ることだし、手間暇を惜しんではならないことを身をもって体験できる。家庭菜園であれば、いろいろな作物をモザイク状に植えたほうがいいのだろう。除草もほどほどが良いのかもしれない。
北海道の農業は機械と農薬によって大規模化が進んでいる。しかし、そのしわ寄せがあとからくるのだ。農業に限らず、何でも利便性を追求していたら、やがてそのしわ寄せがドッと押し寄せてくるのだろう。人が生物であり生態系の一員である以上、大規模化や利便性追及はほどほどにしなければならないと思う。
実際に、農薬・機械まかせの大規模農家が大多数を占める一方で、無農薬有機栽培で頑張っている小規模農家も少数ながらある。どちらが自然と共存した健全なスタイルなのかは言うまでもない。
一極集中を目指して大都市ばかり人口が増え続け、地方は過疎化が進むという構造も同じではなかろうか。大地震などの大災害に襲われれば、大都市はひとたまりもないだろう。大きな被害を出すうえに復興にはとんでもない時間と費用がかかる。地方で大地震が起きても被害が少ないのは歴然とした事実だ。東京にあれほどの高層ビル群を建ててしまったことは間違いだったと思わざるを得ない。方針転換をして地方を大事にすべきだと思う。
北海道では、都市近郊の大型店の増加も地方の小売店を潰してきた。住んでいる地域で買い物ができなければ、高齢者などの弱者を切り捨てることになる。大企業、大型店ばかり優遇すれば、そのツケが必ず弱者に回ってくる。そして過疎化が進めば、医療も福祉も切り捨てられる。
発電にしても、大形の発電所に頼るのではなく、できる限りそれぞれの地域で賄うシステムにしていくべきではないか。メガソーラーも疑問だ。地方に人を分散させ、電気もできる限り地域で自給自足できるようにする政策こそ必要なのではなかろうか。
人間の欲望は尽きない。しかし、そろそろこの矛盾に気づいて方向転換しないと、取り返しのつかないことになるだろう。もう、その分岐点を過ぎてしまったかもしれないが・・・。
2012年04月27日
失われゆく沼沢地の原風景
25・26日に紋別方面に出かけた。雪の多かった北海道もだいぶ雪解けが進み、渚滑川や湧別川の河畔にはアズマイチゲの群落が清楚な花をつけていた。いよいよ春の到来だ。

25日の夜はコムケ湖畔の駐車場で車中泊をした。この季節、こんなところで泊まるような人はまずいない。夕闇の迫る湖面にハクチョウやカモたちの鳴き声が響き渡る。湖畔のヤチハンノキではノビタキがのびやかな声で囀っている。こんな景色を見ながら食事をするのはこの上ない贅沢だ。

私は山も好きだが、沼や湿原の風景もたまらなく好きだ。学生時代にシギやチドリを見るために全国の干潟や湿地をほっつき歩いたことも影響しているのかもしれない。とりわけ北国の荒涼とした沼沢地の風景は、はるか遠いシギの繁殖地の光景を連想させる。
本州に比べたら北海道はまだ湿地や沼地が自然の状態で残っているのだろう。釧路湿原、サロベツ原野、浜頓別から猿払にかけての一帯、オホーツク海沿岸の湖沼地帯、十勝地方の海岸部にある湖沼地帯などなど・・・。とはいっても、沼の周辺の湿地は埋めたれられて農地へと変わってしまったところも少なくない。湿地の原風景は失われつつある。
さらにがっかりするのがキャンプ場の出現だ。日本人は湖があるとキャンプ場をつくりたがる。トイレと炊事場だけの簡素なキャンプ場ならまだしも、たいていは立派な管理棟を造り、街灯を煌々と灯すのだ。シャワーまで付いているところもある。キャンプサイトは芝をはってきれいに整備されている。至れり尽くせりなのだが、せっかく野外で過ごすのになぜこんなに文明を持ち込んでしまうのだろう。
結局、日本人のアウトドアなどブームにすぎないのだろう。だから、ブームが過ぎ去ればキャンプ場は閑散とし、維持管理費ばかりがかさむことになる。廃れてしまったキャンプ場も少なくない。だいたい所狭しとテントが並ぶキャンプ場では、隣のテントの人たちの声は筒抜けだし、夜中まで騒いでいる人も多い。こんなところにはタダでも泊まりたくない。こういう整備されたキャンプ場を利用する人たちは、自然の楽しみ方を知らないのだろう。しかも北海道はキャンプの季節など夏を中心とした数か月しかない。そのために大々的な施設を造るなど愚の骨頂だ。
10年ほど前に行ったサハリンでは、人々は週末になると何の施設もない湿地のほとりや渓流のほとりにテントを張ってキャンプを楽しんでいた。彼らのほうがはるかに自然の楽しみ方、付き合い方を心得ている。
自然の楽しみ方を知っている人なら、そもそも大規模なキャンプ場など造ろうとは思わないのではなかろうか。景観破壊、自然破壊でしかないからだ。結局、地元の町村はお客さんに来てもらいたいがために、キャンプ場などを整備するのだ。整備の先には必ずお金儲けがある。そうやって自然の原風景がどんどん失われていく。
サハリンには北海道によく似た沼沢地があちこちにある。北海道で失われつつある原風景がまだ残されている。湖沼地帯に施設はいらないし、北海道に今残されている原風景をそのまま子孫に残しておいてほしいと願わずにいられない。

25日の夜はコムケ湖畔の駐車場で車中泊をした。この季節、こんなところで泊まるような人はまずいない。夕闇の迫る湖面にハクチョウやカモたちの鳴き声が響き渡る。湖畔のヤチハンノキではノビタキがのびやかな声で囀っている。こんな景色を見ながら食事をするのはこの上ない贅沢だ。

私は山も好きだが、沼や湿原の風景もたまらなく好きだ。学生時代にシギやチドリを見るために全国の干潟や湿地をほっつき歩いたことも影響しているのかもしれない。とりわけ北国の荒涼とした沼沢地の風景は、はるか遠いシギの繁殖地の光景を連想させる。
本州に比べたら北海道はまだ湿地や沼地が自然の状態で残っているのだろう。釧路湿原、サロベツ原野、浜頓別から猿払にかけての一帯、オホーツク海沿岸の湖沼地帯、十勝地方の海岸部にある湖沼地帯などなど・・・。とはいっても、沼の周辺の湿地は埋めたれられて農地へと変わってしまったところも少なくない。湿地の原風景は失われつつある。
さらにがっかりするのがキャンプ場の出現だ。日本人は湖があるとキャンプ場をつくりたがる。トイレと炊事場だけの簡素なキャンプ場ならまだしも、たいていは立派な管理棟を造り、街灯を煌々と灯すのだ。シャワーまで付いているところもある。キャンプサイトは芝をはってきれいに整備されている。至れり尽くせりなのだが、せっかく野外で過ごすのになぜこんなに文明を持ち込んでしまうのだろう。
結局、日本人のアウトドアなどブームにすぎないのだろう。だから、ブームが過ぎ去ればキャンプ場は閑散とし、維持管理費ばかりがかさむことになる。廃れてしまったキャンプ場も少なくない。だいたい所狭しとテントが並ぶキャンプ場では、隣のテントの人たちの声は筒抜けだし、夜中まで騒いでいる人も多い。こんなところにはタダでも泊まりたくない。こういう整備されたキャンプ場を利用する人たちは、自然の楽しみ方を知らないのだろう。しかも北海道はキャンプの季節など夏を中心とした数か月しかない。そのために大々的な施設を造るなど愚の骨頂だ。
10年ほど前に行ったサハリンでは、人々は週末になると何の施設もない湿地のほとりや渓流のほとりにテントを張ってキャンプを楽しんでいた。彼らのほうがはるかに自然の楽しみ方、付き合い方を心得ている。
自然の楽しみ方を知っている人なら、そもそも大規模なキャンプ場など造ろうとは思わないのではなかろうか。景観破壊、自然破壊でしかないからだ。結局、地元の町村はお客さんに来てもらいたいがために、キャンプ場などを整備するのだ。整備の先には必ずお金儲けがある。そうやって自然の原風景がどんどん失われていく。
サハリンには北海道によく似た沼沢地があちこちにある。北海道で失われつつある原風景がまだ残されている。湖沼地帯に施設はいらないし、北海道に今残されている原風景をそのまま子孫に残しておいてほしいと願わずにいられない。
2011年09月17日
函岳の自然
15日は道北の函岳に行ってきた。といっても、この山の頂上には北海道開発局旭川建設部道北レーダー雨雪量計局舎があり、山頂まで車で行ける。もちろん砂利道だが、道はよく整備されている。林道入口には加須美峠まで17km、函岳まで27kmとある。舗装道路なら27kmの道のりはたいしたことはないが、砂利道なのでかなり長い。
麓から中腹にかけては針広混交林なのだが、雪が多いためか針葉樹は少ない。おそらく過去の伐採でさらに減ってしまったのだろう。広葉樹の中にトドマツやエゾマツが点々とあるだけで、林床は丈の高いチシマザサが生い茂っている。チシマザサの高さからも、積雪が非常に多いことが分かる。
北海道の場合、低山帯は針広混交林で標高が上がるにつれて針葉樹が優先する森林となり、針葉樹林帯の上部にはダケカンバ帯があるのが一般的だ。しかし、このあたりは針葉樹林帯がないため、標高が増すに従い針広混交林からダケカンバ帯に移行していく。加須美峠に近づくと、ダケカンバが主体となり、風の強い斜面はハイマツやササとなっている。あまり風が強いとダケカンバは生育できないのだろう。函岳の頂上に近くなるとハイマツとササがモザイク状になっている。
ダケカンバの樹形が面白い。下は加須美峠から函岳にかけて見られるダケカンバ林の写真だ。枝が素直に斜め上に伸びられず、のたうちまわるように曲がりくねっているし、枝が折れている木も多い。風が強いことと雪の重みによる枝折れなのだろう。こんな樹形のダケカンバはあまり見たことがない。


加須美峠から函岳まではなだらかな稜線上に道がつけられているのだが、風当たりの強い稜線では、ダケカンバは矮性化している。

山頂の駐車場には立派な小屋「函岳ヒュッテ」が建っていて、トイレもある。

こちらが道北レーダー雨雪量計局舎。

山頂はレーダーのすぐ裏手だ。晴れていると利尻富士が見えるらしいのだが、この日は生憎の曇り空で遠方の景色は望めなかった。標高1129mのなだらかな地形の山だが、ほとんどが安山岩溶岩と同質火砕岩からなる山なのだそうだ。つまり、ほぼ全体が溶岩でできている山だ。

ハイマツの下にはコケモモやエゾイソツツジ、ゴゼンタチバナなどが見られる。

山頂近くの道路脇には外来種のカラマツも・・・。野鳥などが種子を運んで芽生えたのだろうか。

函岳はライダーに人気の場所で、彼らの間では美深から函岳に向かう林道は「道北スーパー林道」とか「函岳レーダー道路」などと呼ばれているらしい。とくに、加須美峠から先は稜線に道がついており、とても眺めがいいのだ。この日はライダーは少なかったが、バスとすれ違ったのには驚いた。
山の上の観測施設といえば、信州の乗鞍岳に建設されたコロナ観測所や霧ケ峰の車山気象レーダー観測所が頭に浮かぶ。どちらもその人工的な建造物が自然の景観を台無しにしているのは言うまでもない。山の上に大きな施設を造るためには道路を付けなければならないし、道路を通せば必ず自然破壊が生じる。乗鞍岳も車山も観測施設によってずいぶん傷つけられた。乗鞍岳に観光道路がつけられたのも、コロナ観測所への道があったからではなかろうか。あの観光道路で乗鞍岳の自然は大きく損なわれてしまったのだ。
観測施設とはいえ、どこまでこのような施設が必要なのかと、複雑な思いに駆られてしまう。
2011年08月07日
店主の心意気が伝わってくるいわた書店
北海道新聞の日曜日の2面に「サンデー討論」という対論形式のコーナーがある。今日のそのコーナーを見て、思わず目が釘付けになった。
今回のテーマは「マチの本屋はどうあるべきか」。発言されているお二人のうちの一人は、砂川の「いわた書店」の岩田徹さんだ。
私は昨年「小さな街の書店のゆくえ」という記事を書いたのだが、実はここで取り上げている書店とは、この「いわた書店」なのだ。書店の名前は記憶になかったが、これを読んですぐに「あの本屋さんだ!」とピンときた。
私は上記のブログ記事で「もちろん大きな書店ではありませんが、驚いたのは社会系の本が充実していたこと。ふつうこの規模の書店では、雑誌とか実用本、話題になっている本やベストセラーの本などが主流です。どうみても、売れる本を売ろうというのではなく、売りたい本を売るという、店主の主張が伝わってくる選本です」と書いた。
サンデー討論で岩田さんはこんなことを言っている。
「かつて砂川でも大きな書店の進出がありました。40坪対200坪、同じ土俵じゃ負けちゃいます。量より質で活路を見出しました」
「店内も工夫しています。市立病院が近いので医療関係の本や、僕が一番売りたいと思う本を手前に置きます・・・」
私の感じた通りだった。たとえ小さな街の小さな本屋さんでも、お客さんのニーズを知り、店内の配置もきめ細かい工夫をする。そして、店主が本の仕入れを実に念入りにやっていることが、この記事からしっかりと伝わってくる。
岩田さんは最後にこう言っている。
「その町のお客さんを覚え、その人に向けた本を並べられたら、マチの本屋は十分やっていけると思います」
その通りだと思う。今は大型店ばかりが人気だが、お店というのは大きければいいというものではない。あまりにも大きな書店では検索機で在庫の有無や置かれている棚を確認しなければ本を探すのも大変だし、これでは何とも味気ない。自分の居住する地域にあって限られたスペースに「光る一冊」を見つけられる書店、お客さんの意向をきめ細かく汲み取って仕入れに活かす書店こそ、充実しているといえるのではないだろうか。
いわた書店のHPを覗いてみた。トップページを読むだけで、店主の心意気が伝わってくる。
http://homepage3.nifty.com/iwata/
【8月8日追記】
北海道新聞の記事は、いわた書店のサイト(波乱万丈いわた書店日記)で紹介されている。
http://homepage3.nifty.com/iwata/
今回のテーマは「マチの本屋はどうあるべきか」。発言されているお二人のうちの一人は、砂川の「いわた書店」の岩田徹さんだ。
私は昨年「小さな街の書店のゆくえ」という記事を書いたのだが、実はここで取り上げている書店とは、この「いわた書店」なのだ。書店の名前は記憶になかったが、これを読んですぐに「あの本屋さんだ!」とピンときた。
私は上記のブログ記事で「もちろん大きな書店ではありませんが、驚いたのは社会系の本が充実していたこと。ふつうこの規模の書店では、雑誌とか実用本、話題になっている本やベストセラーの本などが主流です。どうみても、売れる本を売ろうというのではなく、売りたい本を売るという、店主の主張が伝わってくる選本です」と書いた。
サンデー討論で岩田さんはこんなことを言っている。
「かつて砂川でも大きな書店の進出がありました。40坪対200坪、同じ土俵じゃ負けちゃいます。量より質で活路を見出しました」
「店内も工夫しています。市立病院が近いので医療関係の本や、僕が一番売りたいと思う本を手前に置きます・・・」
私の感じた通りだった。たとえ小さな街の小さな本屋さんでも、お客さんのニーズを知り、店内の配置もきめ細かい工夫をする。そして、店主が本の仕入れを実に念入りにやっていることが、この記事からしっかりと伝わってくる。
岩田さんは最後にこう言っている。
「その町のお客さんを覚え、その人に向けた本を並べられたら、マチの本屋は十分やっていけると思います」
その通りだと思う。今は大型店ばかりが人気だが、お店というのは大きければいいというものではない。あまりにも大きな書店では検索機で在庫の有無や置かれている棚を確認しなければ本を探すのも大変だし、これでは何とも味気ない。自分の居住する地域にあって限られたスペースに「光る一冊」を見つけられる書店、お客さんの意向をきめ細かく汲み取って仕入れに活かす書店こそ、充実しているといえるのではないだろうか。
いわた書店のHPを覗いてみた。トップページを読むだけで、店主の心意気が伝わってくる。
http://homepage3.nifty.com/iwata/
【8月8日追記】
北海道新聞の記事は、いわた書店のサイト(波乱万丈いわた書店日記)で紹介されている。
http://homepage3.nifty.com/iwata/
2011年06月01日
アイヌ墓地発掘問題でシンポジウム
北海道内でも、あまり多くの人に知られていないのだが「アイヌ墓地発掘問題」というのがある。かつて北海道大学などの人類学者や解剖学者がアイヌの墓地を発掘して遺骨を持ち出したのだが、遺族の了解なしに発掘が行われたり、副葬品が持ち去られたりした。小川隆吉さんは、発掘の真相を知るために北海道大学に情報開示請求を行い、次第にその実態があきらかになってきた。遺骨はどう扱われ、副葬品はどこに行ったのか? 以下は、この問題を考えるシンポジウムの案内である。
**********
公開シンポジウム
『さまよえる遺骨たち』 アイヌ墓地“発掘”の現在
<開催の主旨>
北海道(日本の近代)には、かねてより「アイヌ人骨問題」が存在することを御存知でありましょう。明治時代より戦後に至るまで、北海道はもとより、樺太、千島においても、人骨の発掘と収集が行なわれてきました。その多くは北海道大学医学部人類学研究室のイニシャチブで行なわれました。1000体余りの御遺骨は、長く北大医学部に保存されてきましたが、アイヌやアイヌ協会などの抗議や要請があって、北大構内に「アイヌ納骨堂」が建立され、収蔵されております。毎年、イチャルパも行われておりますが、発掘をめぐる歴史的経緯やその真相が明らかにされたとは言えない状況にあります。遺骨の今後をどうするのかも問題があると言わねばなりません。
また、発掘に伴い多くの副葬品が出土したはずですが、その多くの行方が分からなくなっているようです。小川隆吉さんは北海道大学に「アイヌ人骨」問題に関わる文書の開示を求め、交渉を続けてきました。それなりの文書が開示され、それを読む研究会が行なわれております。研究会は人骨問題をめぐる歴史的経緯と真相をさらに公開するよう北大と交渉してきましたが、事態は進展しているとはいえません。「アイヌ人骨問題」と副葬品問題の今日の状況をみなさまにお伝えし、共にお考えいただきたく、集いを計画いたしました。
さまよえる遺骨たち アイヌ墓地“発掘”の現在
日 時: 2011年6月10日(金) 18:30〜21:00
会 場: 札幌エルプラザ中研修室 札幌市北区北8条西3丁目 TEL:011-728-1222(代表)
参加料: 無料(申し込み不要です。シンポ資料を500円でお分けします)
プログラム:(変更される場合があります)
報告1「私が北大に文書開示請求した理由」 小川隆吉さん(アイヌ長老会議)
報告2「暴かれたお墓の真実」 城野口ユリさん(浦河文化保存会、少数民族懇談会)
講演「なぜ遺骨問題なのか—歴史的背景」 植木哲也さん(苫小牧駒澤大学)
パネルディスカション「さまよえる遺骨たち」
パネリスト(敬称略、順不同)小川隆吉/城野口ユリ/清水裕二/植木哲也ほか
コーディネーター 殿平善彦
集いの提言
主 催: 北大開示文書研究会 TEL(FAX)0164-43-0128
後 援: 少数民族懇談会、強制連行・強制労働犠牲者を考える北海道フォーラム、さっぽろ自由学校「遊」
<北大開示文書研究会>
2008年3月から9月にかけて、小川隆吉氏が北海道大学から開示を受けた「北海道大学医学部、児玉作左衛門収集のアイヌ人骨の台帳とそれに関連する文書」など多数の資料を精査し、当時「研究」の名目で道内外でおこなわれたアイヌ墳墓「発掘」の真実を明らかにすることを目的に、2008年8月5日、発足しました。工芸家、団体職員、教員、僧侶、牧師、会社員、ジャーナリストら約10人で構成。
<アイヌ墓地発掘問題とは>
欧米を中心に「人種学」が隆盛を極めた時代背景のもと、1880年代から1960年代にかけて、和人の人類学者・解剖学者らが道内各地および樺太(現在のサハリン)などのアイヌ墳墓を発掘するなどして大勢の遺骨を収集、研究標本として持ち帰り、測定によってアイヌ「人種」の特徴を見出そうとしました。そのさい、遺族の了解なしに発掘(盗掘)がおこなわれたケースや、遺骨だけでなく副葬品(宝石など)が持ち去られたケースも少なくなかったと考えられます。当時のおもな研究者に小金井良精(1858-1944)・帝国大学医科大学教授、清野謙次(1885-1955)・京都帝国大学医学部教授、児玉作左衛門(1895-1970)・北海道大学医学部教授らがいます。
北海道大学医学部では、そのように収集した大量の遺骨を、長年にわたって動物実験施設内などに放置していたことが1980年代に発覚。遺族や北海道ウタリ協会(現・北海道アイヌ協会)の抗議を受けた同医学部が、遺骨の一部(35人分)を遺族に返還したほか、構内に「アイヌ納骨堂」を新設し、残る遺骨(929人分)を安置し直しました。
しかし、アイヌ墳墓からの「発掘」の詳しい実態や、持ち去られた副葬品の行方などが不明のままだったため、2007年から小川隆吉氏が改めて、北海道大学に対して関連資料の開示を請求。これまで計35点分の文書資料が開示されました。
このなかには、児玉作左衛門教授が担当していた「医学部解剖学第二講座」によるリスト「アイヌ民族人体骨発掘台帳(写)」(作成年不明)など、初めて公になった資料が含まれていますが、当時の研究報告書などとも合わせて精査したところ、資料ごとに、遺骨人数や副葬品数、現在の保管状況などに多くの矛盾点が見つかりました。