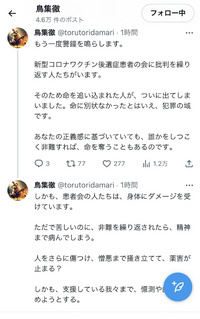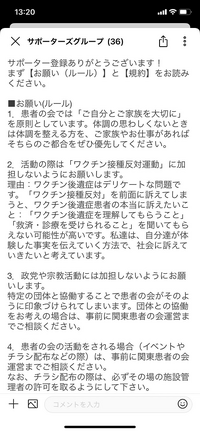2016年02月01日
戦争は人間の本性か?
人間の最も愚かな側面は、戦争と環境破壊だと思う。同じヒトという種でありながら、憎み合って殺し合い、しかも大量殺戮を続けている生物種は地球上にはヒト1種しかいないだろう。環境破壊は、生物の生存基盤そのものを壊したり汚染することで自ら首を絞める行為だ。戦争は同種の殺戮と同時に環境破壊ももたらす。ともに理性のある者がとる行動ではなかろう。
放射能汚染も同じで、お金に目がくらんだ人たちが危険きわまりない原子力の利用を促進してきたことが、人類はもとより地球上の生物の生存を脅かしている。21世紀における人類の選択は、地球上の生物の存続を左右することになるだろう。
しかし、これだけ科学技術が発達した社会でありながら、ヒトはどうして戦争が止められないのだろうか。「戦争はヒトの本性」とか「戦争があるから人口増加が抑えられる」などといったことを口にする人がいるが、本当にそうなのだろうか? やや古い記事だが、以下からもやはり戦いは人間の本性ではないと考えざるを得ない。
「戦いは人間の本質ではなかった」:研究結果
アイヌの人たちはチャランケという弁論よってもめごとの解決を図ったという。アイヌ民族がまったく闘いをしなかったということではないにしても、話し合いで争いごとを解決するというのが彼らの基本的なやり方だったのだろう。
狩猟採取生活をしている少数民族は、自然の中でひっそりと暮らしていて集団で殺し合いをするという話しはまずきかない。以前、NHKのテレビ番組で、狩猟採取生活をしているある民族にはストレスがないと報じていた。彼らは協力して獲物を捉え、食糧を集団の中で平等に分け与える生活をしているが、こうした集団内の協力や平等意識が武力闘争のない平和な生活を維持しているのだろう。狩りに非協力的な自己中な人は、集団内で生きていけないことになる。
だいたい、同種同士で殺し合いをする動物はほとんどいない。チンパンジーなどには子殺しもあるが、これとて憎しみによる集団での殺し合いではない。ところが、人類はあるときから殺し合いをするようになってしまった。人間がいつまでたっても戦争という殺戮を止められないのは、欲を制御できないからとしか思えない。富を溜めこむようになった社会には富の分配の偏りという不平等が生じ、より多くの富を得ようとする競争があり、こうした社会では不平等と闘争心によって自ずとストレスが蓄積する。
富の配分が公平で、支配や競争がない社会であればストレスは生じにくいだろうし、ストレスや競争がなく人と人が協力しあう社会であれば、人が憎み合うことも少ないだろう。ならば、人々が平和な暮らしを続けるために必要なのは、富をできる限り均等に配分して格差をなくし、人々が協力しあう社会を構築することだ。
そして、地球上の資源は限りがあることを自覚し、自然改変をできる限り慎む努力をしつつ再生可能エネルギーを利用していくしかないのではなかろうか。もちろん、だからといって昔のような生活に戻れというつもりはない。自分たちの生存基盤である自然環境の保全を前提にしなければ、どこかで綻びが生じ持続可能な社会は続かない。戦いが人間の本性ではないのなら、意識と努力次第で平和な社会は築けるはずだ。
しかし、日本は正反対の方向に向かっている。格差は拡大するばかりだし、福祉は切り捨て。今や働けど働けど搾取される非正規の労働者と、年金だけで生活できない高齢者が溢れている。あれだけ大きな事故を起こし放射能をばら撒きながら、原発をやめる気配がない。これでは人々の間に不満やストレスがたまり、攻撃的になるのも当たり前だろう。安倍首相は人々を攻撃的にしておいて、戦争に駆り出そうというつもりなのだろうか。
これに気づき、理性を働かせていかないと、ストレスをため感情的、攻撃的になった人間は簡単に騙され誘導されてしまう。はたしてヒトは理性をとりもどし、戦争のない社会を構築することができるのだろうか?
放射能汚染も同じで、お金に目がくらんだ人たちが危険きわまりない原子力の利用を促進してきたことが、人類はもとより地球上の生物の生存を脅かしている。21世紀における人類の選択は、地球上の生物の存続を左右することになるだろう。
しかし、これだけ科学技術が発達した社会でありながら、ヒトはどうして戦争が止められないのだろうか。「戦争はヒトの本性」とか「戦争があるから人口増加が抑えられる」などといったことを口にする人がいるが、本当にそうなのだろうか? やや古い記事だが、以下からもやはり戦いは人間の本性ではないと考えざるを得ない。
「戦いは人間の本質ではなかった」:研究結果
アイヌの人たちはチャランケという弁論よってもめごとの解決を図ったという。アイヌ民族がまったく闘いをしなかったということではないにしても、話し合いで争いごとを解決するというのが彼らの基本的なやり方だったのだろう。
狩猟採取生活をしている少数民族は、自然の中でひっそりと暮らしていて集団で殺し合いをするという話しはまずきかない。以前、NHKのテレビ番組で、狩猟採取生活をしているある民族にはストレスがないと報じていた。彼らは協力して獲物を捉え、食糧を集団の中で平等に分け与える生活をしているが、こうした集団内の協力や平等意識が武力闘争のない平和な生活を維持しているのだろう。狩りに非協力的な自己中な人は、集団内で生きていけないことになる。
だいたい、同種同士で殺し合いをする動物はほとんどいない。チンパンジーなどには子殺しもあるが、これとて憎しみによる集団での殺し合いではない。ところが、人類はあるときから殺し合いをするようになってしまった。人間がいつまでたっても戦争という殺戮を止められないのは、欲を制御できないからとしか思えない。富を溜めこむようになった社会には富の分配の偏りという不平等が生じ、より多くの富を得ようとする競争があり、こうした社会では不平等と闘争心によって自ずとストレスが蓄積する。
富の配分が公平で、支配や競争がない社会であればストレスは生じにくいだろうし、ストレスや競争がなく人と人が協力しあう社会であれば、人が憎み合うことも少ないだろう。ならば、人々が平和な暮らしを続けるために必要なのは、富をできる限り均等に配分して格差をなくし、人々が協力しあう社会を構築することだ。
そして、地球上の資源は限りがあることを自覚し、自然改変をできる限り慎む努力をしつつ再生可能エネルギーを利用していくしかないのではなかろうか。もちろん、だからといって昔のような生活に戻れというつもりはない。自分たちの生存基盤である自然環境の保全を前提にしなければ、どこかで綻びが生じ持続可能な社会は続かない。戦いが人間の本性ではないのなら、意識と努力次第で平和な社会は築けるはずだ。
しかし、日本は正反対の方向に向かっている。格差は拡大するばかりだし、福祉は切り捨て。今や働けど働けど搾取される非正規の労働者と、年金だけで生活できない高齢者が溢れている。あれだけ大きな事故を起こし放射能をばら撒きながら、原発をやめる気配がない。これでは人々の間に不満やストレスがたまり、攻撃的になるのも当たり前だろう。安倍首相は人々を攻撃的にしておいて、戦争に駆り出そうというつもりなのだろうか。
これに気づき、理性を働かせていかないと、ストレスをため感情的、攻撃的になった人間は簡単に騙され誘導されてしまう。はたしてヒトは理性をとりもどし、戦争のない社会を構築することができるのだろうか?
この記事へのコメント
私は、アイヌ民族のチャランケに関して、もめごとの解決・回避の機能はあったでしょうが、限定的だったと考えています。
戦い、争いということでは「シャクシャインの戦い(1669年)」など複数回の対和人闘争がありました。千島列島ウルップ島では、抗争したロシア人20人を殺害しています(1771年)。これら異民族との戦いでは当然ながら、奇襲が多く、チャランケは機能していません。
同族同士では根室アイヌが宗谷アイヌを攻め六十人余を殺害(1758年)、十勝アイヌと沙流(日高)アイヌが抗争(1770年)、十勝利別川の漁猟権をめぐり十勝アイヌと網走アイヌが紛争(1837年)などがあります。豊頃町の旅来(たびこらい)チャシには、地元の酋長が「タップカラ」という踏舞を踊って戦死したという伝承があり、それが1770年の抗争にまつわる出来事などと言われています。こうした戦いでは、戦闘の前段でチャランケが述べられることもあるようですが、それは戦い前のセレモニー的な感があります。
また伝承のレベルですが、帯広市のチョマトー(沼)、売買川にも日高アイヌのとの抗争にまつわるものがあります。私の故郷である十勝利別川流域には北見アイヌの集団などがやって来る「トバットミ(略奪行為)」行為の伝承、浦幌町厚内チャシにも抗争の伝承があります。江戸時代のアイヌ民族の人口が樺太、千島も含め最大二万五千人程度だったことを思うと、「自然を愛する平和な民族」というのは皮相なとらえ方ではないでしょうか。当時のアイヌ民族人口が最大二万五千人程度だったことを思うと、異民族、同族間で相当な抗争があったと考えています。
またチャランケに関しては、例えば言いがかりをつけ財産を奪うとか、あるいは蝦夷地を訪れた和人に対して、タブー違反をとがめてツグナイ(つぐない)品を取る、といったことが記録されています。例えば「死者に関して言及しない」というタブーがあり、それを知らない和人が再訪して「おや、おじいさんの姿が見えませんが、どうしましたか?」などと聞いたりしたケースです。このために「蝦夷地に入って商売する場合は、先達(経験者)についていけ」などと言われました。アイヌ民族が自然と共に生きたすばらしい人々であると思いますが、妖精のような人々というような理解は皮相だと考えています。オホーツク海をはさんで大陸や千島列島に雄飛した交易の民、というのが実態に近いのではないのでしょうか。
なお北海道弁では、アイヌ語から引用した「チャランケをつける」という言い回しがあり、ほぼ「いいがかり、因縁をつける」と同義で用いられています。なんとも品のない言い回しですが、実際にそうした使用例があったから、という気もしています。
戦い、争いということでは「シャクシャインの戦い(1669年)」など複数回の対和人闘争がありました。千島列島ウルップ島では、抗争したロシア人20人を殺害しています(1771年)。これら異民族との戦いでは当然ながら、奇襲が多く、チャランケは機能していません。
同族同士では根室アイヌが宗谷アイヌを攻め六十人余を殺害(1758年)、十勝アイヌと沙流(日高)アイヌが抗争(1770年)、十勝利別川の漁猟権をめぐり十勝アイヌと網走アイヌが紛争(1837年)などがあります。豊頃町の旅来(たびこらい)チャシには、地元の酋長が「タップカラ」という踏舞を踊って戦死したという伝承があり、それが1770年の抗争にまつわる出来事などと言われています。こうした戦いでは、戦闘の前段でチャランケが述べられることもあるようですが、それは戦い前のセレモニー的な感があります。
また伝承のレベルですが、帯広市のチョマトー(沼)、売買川にも日高アイヌのとの抗争にまつわるものがあります。私の故郷である十勝利別川流域には北見アイヌの集団などがやって来る「トバットミ(略奪行為)」行為の伝承、浦幌町厚内チャシにも抗争の伝承があります。江戸時代のアイヌ民族の人口が樺太、千島も含め最大二万五千人程度だったことを思うと、「自然を愛する平和な民族」というのは皮相なとらえ方ではないでしょうか。当時のアイヌ民族人口が最大二万五千人程度だったことを思うと、異民族、同族間で相当な抗争があったと考えています。
またチャランケに関しては、例えば言いがかりをつけ財産を奪うとか、あるいは蝦夷地を訪れた和人に対して、タブー違反をとがめてツグナイ(つぐない)品を取る、といったことが記録されています。例えば「死者に関して言及しない」というタブーがあり、それを知らない和人が再訪して「おや、おじいさんの姿が見えませんが、どうしましたか?」などと聞いたりしたケースです。このために「蝦夷地に入って商売する場合は、先達(経験者)についていけ」などと言われました。アイヌ民族が自然と共に生きたすばらしい人々であると思いますが、妖精のような人々というような理解は皮相だと考えています。オホーツク海をはさんで大陸や千島列島に雄飛した交易の民、というのが実態に近いのではないのでしょうか。
なお北海道弁では、アイヌ語から引用した「チャランケをつける」という言い回しがあり、ほぼ「いいがかり、因縁をつける」と同義で用いられています。なんとも品のない言い回しですが、実際にそうした使用例があったから、という気もしています。
Posted by 中尾 at 2016年02月25日 14:34
中尾さん
詳しい情報およびご意見、ありがとうございました。
アイヌにおいても同族内での戦いがあったことは存じています。ご指摘のあったチョマトーは道路の改修工事で半分以上が埋め立てられてしまいましたが、十勝自然保護協会はこの埋め立てに反対した経緯があり、ここでアイヌの抗争があったとの言い伝えは知っていました。また十勝アイヌと網走アイヌの紛争なども聞いたことがあります。狩猟採取民族であってもかなり広範な行動権をもっていたアイヌにとって、資源などをめぐり近隣の集団間での争いが生じたのはある意味当然のこととも思います。
チャランケが紛争解決にどのていどの役割を果たしていたのかは分かりませんが、同じ集団の中での紛争の解決や回避の機能はあっても、集団間においての紛争回避の機能はあまりなかったのかもしれませんね。
ただし、アイヌにとって戦いが本性であったかどうかという点においては、そうではなかったのではないかと思います。北海道の厳しい環境の中で生きていかねばならない狩猟採取民族にとって、衣食住のための資源の確保は死活問題ですから、集団が生きのびるためには時として体を張っての争いもやむを得なかったという事情もあったのではないでしょうか。
狩猟採取民族といっても資源が乏しく厳しい環境の地に暮らさざるを得ない民族と、温暖で資源の豊富なところに暮らす民族では、戦いについて同列に見ることはできないように思います。
「チャランケをつける」という表現や意味については知りませんでしたので、認識を新たにしました。
詳しい情報およびご意見、ありがとうございました。
アイヌにおいても同族内での戦いがあったことは存じています。ご指摘のあったチョマトーは道路の改修工事で半分以上が埋め立てられてしまいましたが、十勝自然保護協会はこの埋め立てに反対した経緯があり、ここでアイヌの抗争があったとの言い伝えは知っていました。また十勝アイヌと網走アイヌの紛争なども聞いたことがあります。狩猟採取民族であってもかなり広範な行動権をもっていたアイヌにとって、資源などをめぐり近隣の集団間での争いが生じたのはある意味当然のこととも思います。
チャランケが紛争解決にどのていどの役割を果たしていたのかは分かりませんが、同じ集団の中での紛争の解決や回避の機能はあっても、集団間においての紛争回避の機能はあまりなかったのかもしれませんね。
ただし、アイヌにとって戦いが本性であったかどうかという点においては、そうではなかったのではないかと思います。北海道の厳しい環境の中で生きていかねばならない狩猟採取民族にとって、衣食住のための資源の確保は死活問題ですから、集団が生きのびるためには時として体を張っての争いもやむを得なかったという事情もあったのではないでしょうか。
狩猟採取民族といっても資源が乏しく厳しい環境の地に暮らさざるを得ない民族と、温暖で資源の豊富なところに暮らす民族では、戦いについて同列に見ることはできないように思います。
「チャランケをつける」という表現や意味については知りませんでしたので、認識を新たにしました。
Posted by 松田まゆみ at 2016年02月25日 23:21
at 2016年02月25日 23:21
 at 2016年02月25日 23:21
at 2016年02月25日 23:21ご丁寧なお返事ありがとうございます。
もちろん私も、人間は本来、争いを回避するノウハウを身に着けた生物種だと考えています。
それは「一夫一婦制(原則的)」などにも表れています。荒野で初対面の人と出くわした場合に、あいさつすることも覚えました。
そうしたノウハウがあるけれど近代国家、集団意識というものが大きな問題だと思います。「朝鮮人がどうの」というヘイトスピーチ。本当に始末が悪く、御しがたい争いへの原動力になってしまっています。経済格差なども、信じられないほど大きくなってしまいました。
もちろん私も、人間は本来、争いを回避するノウハウを身に着けた生物種だと考えています。
それは「一夫一婦制(原則的)」などにも表れています。荒野で初対面の人と出くわした場合に、あいさつすることも覚えました。
そうしたノウハウがあるけれど近代国家、集団意識というものが大きな問題だと思います。「朝鮮人がどうの」というヘイトスピーチ。本当に始末が悪く、御しがたい争いへの原動力になってしまっています。経済格差なども、信じられないほど大きくなってしまいました。
Posted by 中尾 at 2016年02月29日 16:02
中尾さん
おっしゃる通り、競争や経済格差が憎しみや復讐心を増幅させているように思います。過度の競争や格差の解消はもちろん大事ですが、それと同時に個人個人の精神面での自立が求められているように思います。
おっしゃる通り、競争や経済格差が憎しみや復讐心を増幅させているように思います。過度の競争や格差の解消はもちろん大事ですが、それと同時に個人個人の精神面での自立が求められているように思います。
Posted by 松田まゆみ at 2016年02月29日 16:20
at 2016年02月29日 16:20
 at 2016年02月29日 16:20
at 2016年02月29日 16:20 渡島管内八雲町にある縄文時代前期の遺跡、栄浜1遺跡に9遺体を一つのお墓にまとめて埋葬した合葬墓があります。
この9遺体とともに石の矢尻が5点出土して、調査報告書はこの9遺体は何らかの争いの犠牲者と推測しています。(石の矢尻5点で9人分の死因にはなりませんが、たぶん遠方から矢を射て、続いて棍棒でなぐるような接近戦闘が行われたのでしょう)
縄文時代にも争いが全くなかったわけではないことが明らかになっていますが、9人が一度に犠牲になるというのは、全国的にもとても珍しいケースです。とはいえ、この報告はあまり考古学会で取り上げられることもなく、北海道新聞でも一度も記事になっていないのは驚きです。
縄文時代のような狩猟採集経済であっても、階層化が進んでいた、という見解は最近、有力になっています。とりわけ北緯40度以北で顕著で、これは例えば北米太平洋岸のトリンギット族(三浦綾子さんの小説「海嶺」に出てくる、江戸時代の日本人が漂着して奴隷にされ、いけにえとして首をはねられそうになった)なども有名です。
北緯40度以北で階層化を進めた要因は、サケ漁労を柱とする資源の豊富さです。私の推測ですが、八雲町という場所は道南の大河、遊楽部川がありサケや前浜の資源が豊富で、それが争いの動機となったのかもしれません。
この9遺体とともに石の矢尻が5点出土して、調査報告書はこの9遺体は何らかの争いの犠牲者と推測しています。(石の矢尻5点で9人分の死因にはなりませんが、たぶん遠方から矢を射て、続いて棍棒でなぐるような接近戦闘が行われたのでしょう)
縄文時代にも争いが全くなかったわけではないことが明らかになっていますが、9人が一度に犠牲になるというのは、全国的にもとても珍しいケースです。とはいえ、この報告はあまり考古学会で取り上げられることもなく、北海道新聞でも一度も記事になっていないのは驚きです。
縄文時代のような狩猟採集経済であっても、階層化が進んでいた、という見解は最近、有力になっています。とりわけ北緯40度以北で顕著で、これは例えば北米太平洋岸のトリンギット族(三浦綾子さんの小説「海嶺」に出てくる、江戸時代の日本人が漂着して奴隷にされ、いけにえとして首をはねられそうになった)なども有名です。
北緯40度以北で階層化を進めた要因は、サケ漁労を柱とする資源の豊富さです。私の推測ですが、八雲町という場所は道南の大河、遊楽部川がありサケや前浜の資源が豊富で、それが争いの動機となったのかもしれません。
Posted by 中尾 at 2016年03月04日 10:09
中尾さん
貴重な情報をありがとうございました。
狩猟採取生活であっても集団間ではおそらく様々なトラブルがあったのでしょう。たとえば資源をめぐって話し合いでの解決が図れないとか、一方的に攻撃されるなどということがあれば、やはり戦いにならざるを得なかったのでしょうか。
貴重な情報をありがとうございました。
狩猟採取生活であっても集団間ではおそらく様々なトラブルがあったのでしょう。たとえば資源をめぐって話し合いでの解決が図れないとか、一方的に攻撃されるなどということがあれば、やはり戦いにならざるを得なかったのでしょうか。
Posted by 松田まゆみ at 2016年03月04日 11:30
at 2016年03月04日 11:30
 at 2016年03月04日 11:30
at 2016年03月04日 11:30※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。